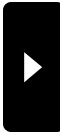4月24日の記事
2023年04月24日
こんにちは。
2年以上の空白を経て、新たにまた記事投稿していきます。空白は、単なる私的な事情でしたので、2023年の春を迎え新しい情報の共有を念頭に進めて参ります。またコロナウィルスの猛威や世界的な政治経済の混乱に負けず、過ごしていらした皆さんに、敬意を表し今後の更なる頑張りを少しでも応援できるように邁進していきます。
年代を問わず、いつも英語は必要になるもの。。その学び方と教え方を中心に投稿を続けて行くつもりです。
それに先立ち、英語学習や現在の英語教育の現状についての考察から始めるすもりです。
1.英語のより良い学び方: ネットや、マスメディアで流れる情報に翻弄されず自分の学び方を発見すること
2.現在の義務教育制度下の英語教育とは
3.将来へ向けての英語の位置づけ
4.今後、当教室がなすべきこと
この4点に加え、独自の視点で言語としての英語習得の道を模索していきましょう。
2年以上の空白を経て、新たにまた記事投稿していきます。空白は、単なる私的な事情でしたので、2023年の春を迎え新しい情報の共有を念頭に進めて参ります。またコロナウィルスの猛威や世界的な政治経済の混乱に負けず、過ごしていらした皆さんに、敬意を表し今後の更なる頑張りを少しでも応援できるように邁進していきます。
年代を問わず、いつも英語は必要になるもの。。その学び方と教え方を中心に投稿を続けて行くつもりです。
それに先立ち、英語学習や現在の英語教育の現状についての考察から始めるすもりです。
1.英語のより良い学び方: ネットや、マスメディアで流れる情報に翻弄されず自分の学び方を発見すること
2.現在の義務教育制度下の英語教育とは
3.将来へ向けての英語の位置づけ
4.今後、当教室がなすべきこと
この4点に加え、独自の視点で言語としての英語習得の道を模索していきましょう。
これから英語を身につけるには?
2017年11月16日
本当に久しぶりの投稿です。
この1年半色々なことがあった反面、変わらぬ姿勢で英語教育に取り組んでいます。今後の予定としては以下のようなテーマで記事を書いて行こうと思案中です。
1.仕事、旅行、趣味、そして自己鍛錬としての英語
2.教育改革に伴う今後の英語教育展望
3.中学・高校での英語教育の現場とその望ましい姿と展望
4.英語はどのようにして学ぶのが効果的なのか
5.初等教育での英語教授って必要?
上記は書きたいことのほんの一部です。 現在の繁忙さから抜け出せつつあるため、今後一つ一つを丁寧にかつ現場の経験を盛り込みながら投稿していきます。今後ともよろしくお願いもうしあげます。
学べる英語教室「Good Performer」
小田切
この1年半色々なことがあった反面、変わらぬ姿勢で英語教育に取り組んでいます。今後の予定としては以下のようなテーマで記事を書いて行こうと思案中です。
1.仕事、旅行、趣味、そして自己鍛錬としての英語
2.教育改革に伴う今後の英語教育展望
3.中学・高校での英語教育の現場とその望ましい姿と展望
4.英語はどのようにして学ぶのが効果的なのか
5.初等教育での英語教授って必要?
上記は書きたいことのほんの一部です。 現在の繁忙さから抜け出せつつあるため、今後一つ一つを丁寧にかつ現場の経験を盛り込みながら投稿していきます。今後ともよろしくお願いもうしあげます。
学べる英語教室「Good Performer」
小田切
英語を教えること、学ぶこと。より良い方法は? 英語教室GP
2016年05月14日
こんにちは。季節の移り変わりは速く、新緑、梅雨を経て夏へと移り変わっていきますね。毎年この時期は、改めて今後自分自身が何をしたいのか、また何をすべきなのかを考えるのに良いタイミングとして位置づけいろいろ思いをめぐらすことにしています。
先ずは社会人の方々に実務に必要な英語力を身につけていただくお手伝いをすることは、教室創設当初から変わらぬ最優先事項です。しかし、それに加えてやはり教育制度の中で英語の習得を目指す若い世代の言葉の学び方を、どうにか違った方向に変えていくことで、言葉としての英語を身につけてもらう道を導き出すことが不可欠だと考えざるを得ません。
日本人が英語で英語を教えることは、決して自分自身の英語力を誇示することではなく英語を自然な感覚で身につけてもらうために、英語という言語が持つ日本語とは異なる特徴を上手く伝えていくことにあると考えます。英語は、能力技術である以前に言葉であることを忘れたら、決して身につけることはできません。子供、大人を問わず誰もが見つけることができる単なる言葉であることを出発点として生徒さんたちに接することが何よりも大切です。
言葉は、そもそも話すことから始まったことは周知のことですね。文明の伸展と共に文字が考案され、音声では不可能なコミュニケーションの方法を人間は考え出しました。中等教育(中学・高校)での英語学習に端を発し、日本の英語教育は全く言葉の進化と逆の方向で進められているのは皆さんも経験から感じられていることでしょう。つまり視覚から入って言葉を学ぶことが多いということです。この手法が続く限り、言葉としての英語は永遠に身につくことはありえません。
現在、いや今後求められているのは、言葉の起源である音声による表現力と読み書きができる時代に即応した言語力の両方であることを、再度根本的に認識し、それを形にしていく方法論を確立し実践していくことだと思います。そこで英語を教える側に求められるのは、その方法論を実践していく力の習得であることは、また明らかなことでもあります。
語学学習に、この2つの側面を並行して取り入れていく必要があります。つまり「聞く」「読む」といったインプット作業、そして「話す」「書く」というアウトプットの実践です。教える立場にある者は、この2つのレベルが極めて近い状態になっていないと、教えられる側、つまりは生徒さん達に困惑をもたらし、結果としてしっかりしたコミュニケーション力を習得させることが不可能になります。
当方がいつも教える際に、心に刻み込んでいるのは以下の点です。
1.英語表現のデータベースをしっかり脳の中に作り上げる事: これは読むことと聞くことから実現されるため、その努力を欠かさないこと
2.表現すべきことを日本語からの単なる翻訳作業ではなく、解釈を基盤に適切な英語表現を反射的に創出すること: 脳にあるデータベースから的確に抽出することが不可欠
教室での授業の中で、頻繁に実施することの一つに、Restatementという方法があります。これは、聞いたり、読んだりした英語の意味を出来る限り変えずに異なった英語で言い換える練習です。通訳訓練法の一つにReproductionという手法がありますが、これを短く切ってSentence, Phrase単位で実施していくのが当教室でのRestatementです。これを繰り返すことは、日本語を介在させずに表現したいことを英語で解釈して表現することが可能になります。つまり自分の英語データベースの中から検索して適切な表現を創出することができるようになるということです。
英語には様々な学び方、教え方があってよいのかもしれません。しかし日本語と同じ言葉であることを認識しているのであれば、英語で会話、議論し、英語でメールや手紙、レポート、論文を書くことが出来なければ、それらの学び方、教え方に問題があるということです。
英語を教授される側は、何よりもそのことを忘れてならないことだけは確かなことだと考えます。次回は、もう少し整理した形でまた英語の教え方、学び方を考えようかと思っています。教室での授業に加えて、もうすぐ帰国子女の生徒たちの授業が始まります。その中からもヒントを得ながらまた投稿します。
最後に・・・
中学・高校の英語教員の方々で、今後真剣に英語で教えることをお考えの方々からのお問い合わせを心待ちにしております。英語力、及び英語指導力の向上努力を始めてみませんか。
先ずは社会人の方々に実務に必要な英語力を身につけていただくお手伝いをすることは、教室創設当初から変わらぬ最優先事項です。しかし、それに加えてやはり教育制度の中で英語の習得を目指す若い世代の言葉の学び方を、どうにか違った方向に変えていくことで、言葉としての英語を身につけてもらう道を導き出すことが不可欠だと考えざるを得ません。
日本人が英語で英語を教えることは、決して自分自身の英語力を誇示することではなく英語を自然な感覚で身につけてもらうために、英語という言語が持つ日本語とは異なる特徴を上手く伝えていくことにあると考えます。英語は、能力技術である以前に言葉であることを忘れたら、決して身につけることはできません。子供、大人を問わず誰もが見つけることができる単なる言葉であることを出発点として生徒さんたちに接することが何よりも大切です。
言葉は、そもそも話すことから始まったことは周知のことですね。文明の伸展と共に文字が考案され、音声では不可能なコミュニケーションの方法を人間は考え出しました。中等教育(中学・高校)での英語学習に端を発し、日本の英語教育は全く言葉の進化と逆の方向で進められているのは皆さんも経験から感じられていることでしょう。つまり視覚から入って言葉を学ぶことが多いということです。この手法が続く限り、言葉としての英語は永遠に身につくことはありえません。
現在、いや今後求められているのは、言葉の起源である音声による表現力と読み書きができる時代に即応した言語力の両方であることを、再度根本的に認識し、それを形にしていく方法論を確立し実践していくことだと思います。そこで英語を教える側に求められるのは、その方法論を実践していく力の習得であることは、また明らかなことでもあります。
語学学習に、この2つの側面を並行して取り入れていく必要があります。つまり「聞く」「読む」といったインプット作業、そして「話す」「書く」というアウトプットの実践です。教える立場にある者は、この2つのレベルが極めて近い状態になっていないと、教えられる側、つまりは生徒さん達に困惑をもたらし、結果としてしっかりしたコミュニケーション力を習得させることが不可能になります。
当方がいつも教える際に、心に刻み込んでいるのは以下の点です。
1.英語表現のデータベースをしっかり脳の中に作り上げる事: これは読むことと聞くことから実現されるため、その努力を欠かさないこと
2.表現すべきことを日本語からの単なる翻訳作業ではなく、解釈を基盤に適切な英語表現を反射的に創出すること: 脳にあるデータベースから的確に抽出することが不可欠
教室での授業の中で、頻繁に実施することの一つに、Restatementという方法があります。これは、聞いたり、読んだりした英語の意味を出来る限り変えずに異なった英語で言い換える練習です。通訳訓練法の一つにReproductionという手法がありますが、これを短く切ってSentence, Phrase単位で実施していくのが当教室でのRestatementです。これを繰り返すことは、日本語を介在させずに表現したいことを英語で解釈して表現することが可能になります。つまり自分の英語データベースの中から検索して適切な表現を創出することができるようになるということです。
英語には様々な学び方、教え方があってよいのかもしれません。しかし日本語と同じ言葉であることを認識しているのであれば、英語で会話、議論し、英語でメールや手紙、レポート、論文を書くことが出来なければ、それらの学び方、教え方に問題があるということです。
英語を教授される側は、何よりもそのことを忘れてならないことだけは確かなことだと考えます。次回は、もう少し整理した形でまた英語の教え方、学び方を考えようかと思っています。教室での授業に加えて、もうすぐ帰国子女の生徒たちの授業が始まります。その中からもヒントを得ながらまた投稿します。
最後に・・・
中学・高校の英語教員の方々で、今後真剣に英語で教えることをお考えの方々からのお問い合わせを心待ちにしております。英語力、及び英語指導力の向上努力を始めてみませんか。
英語による英語教授の必要性! 中高英語教員方々へ!
2016年04月03日
こんにちは。いよいよ春本番! 桜も満開の時を迎えました。入学や入社といった新しいスタートに期待と不安の入り混じった気持ちを持って、この季節を迎える方々も多いのではないでしょうか。
当教室も年明け、そして3月から4月へと時が流れる中で、徐々に様相が変わってきています。年初から2月にかけて、他英語スクールから5名、シニアの主婦の方々に入室いただき、今月には新高校生、大学生もそれぞれに合ったコースに参加いただいています。毎年、違った傾向の下で、様々な方々に加わっていただけることは、正に言葉を身につけることに、年齢や状況の相違といった隔たりに、いかなる影響も受けないのだということを改めて実感しています。
そうした変化に後押しされながら、今回からまた英語を身につけることをテーマに書き綴っていきたいと考えます。先日、読売新聞の教育関連欄に興味深い記事を見つけました。それは、中学高校の英語教員の方々が、政府関連機関及び民間機関(例えば、British Council)が実施する「英語による英語教育プログラム」に積極的に参加を開始し始めているという趣旨のものでした。ある英語による英語教授法講座は、応募者が募集人員の数倍に達しているということです。民間機関慰よる講座は、1回の参加料金が10,000円をはるかに超えるにも関わらず、学校教員の方々が英語の運用力を高め現場で英語によるコミュニケーションを実践することは望ましいことです。
これまで、当教室では受験コースを含め英語による英語の授業をレベルに応じて実践して来ました。その中で、いつも気を付けなければならないと思うことはいくつかあります。以下、英語を英語で教授する際の当なりの注意事項です。
1.英語のどの部分を英語で教授するか。コミュニケーションスキル・文法・リーディング素材・エッセイライティング・スピーチまたはプレゼンテーション指導等、項目は多岐に渡るためその一つ一つについて素材を厳選し、教え方のシナリオと構成を考える必要があるということ。
2.英語で教授するための精緻な文法知識が必要となること。
3.自分自身が仕上げたシナリオを十分うまく生徒に伝わるように英語表現力をつけること。この際、特に動詞を中心とするCollocationに十分注意し間違った繋がり表現を教えないこと。
4.間違った発音をしないこと。つまり自分自身でネイティヴスピーカーが話す音を忠実に実現すること。同時に語の「ストレス(協調)」の位置を正確に声にして覚えること。例えば、theを「ザァ」などと決して発音しないことや、adviceを「アドヴァイス」などと日本語発音で発生しないこと等々。
以上の事項は、まだまだほんの一部で研鑽事項はこれらをはるかに超えますが、「英語を英語で教える」ことには、多大な知識と正確な運用力の習得が求められるということを忘れてはならないということです。そして何より大事なのは、無限の可能性を持つ10代の生徒達を英語で教えることには責任が伴うということです。彼らが間違った表現や発音で英語という言葉を身につけてしまうことに、ある意味緊張と恐怖感を持って臨むことは極めて重要です。
当教室の場合は、子供のみならず大人の方々に関しても、英語による教授方法には常に注意を払い臨んでいます。以前より通訳の訓練方法に関して表面的に言及して来ましたが、一部の私立高校などではそれらを英語の授業の中に導入しているようです。よく「シャドウイング」という言葉を耳にされる方々も多いかと思いますが、これは通訳者育成のための一つの訓練方です。別名「Follow」とも呼ばれています。こうした試みは悪いことではないと思いますが、この訓練法の本当の意味を知らず「ネイティヴスピーカーの話す音を、ただ影を追うように追いかけて音声を発するもの」などと間違った考えの基にて教えても何の効果もあがりません。Followに限らず、通訳の訓練法は、常に理解に裏付けされていなければならないということを忘れてしまっては、全く意味のない単なる「やった気分になる練習」で終わってしまいます。ましてや「聞き流し」などはモッテノホカです。
通訳の訓練方法の多くは、今後義務教育での英語教育に限らず、どんな学習者にとっても必要な要素を多く携えています。こうした方法を英語で教える事と融合させれば、中学高校、更には社会人の方々が正に必要としている英語力は習得可能であると考えます。
上記の内容に興味を持たれた方や現役の英語教員の方々の中で、ご自身の英語運用力を更に向上させたいとお考えの方はご遠慮なく連絡ください。政府関連機関、民間機関が提供している講座には限りがあり、まだ頻繁に実施されているわけではありません。当教室では、10年前の創設当初からこの種の講座を企画してきました。プライベイトでの対応、ワークショップ形式での講座実施に向け本格的に始動します。お問い合わせは以下まで。国際化の重大な一助となるべき英語を本気で教える、身につけることをそろそろ考えませんか。
次回は、昨春小学校を卒業して入室してきた男子生徒S太郎くん(市立中学校新中学2年生)の驚くべき英語上達の過去一年に触れながら、年齢に関係ない英語の上達方法も含め今回の話題を発展させていきます。
追伸: S太郎の授業は、この一年ほぼ英語のみで実施してきました。
◆お問い合わせ
「学べる英語教室」 Good Performer グッドパフォーマー
電話: 042-486-2004
e-mail: good-performer@jcom.home.ne.jp
URL: http://chofu.com/good-performer/ (ちょうふどっとこむポータルサイト)
当教室も年明け、そして3月から4月へと時が流れる中で、徐々に様相が変わってきています。年初から2月にかけて、他英語スクールから5名、シニアの主婦の方々に入室いただき、今月には新高校生、大学生もそれぞれに合ったコースに参加いただいています。毎年、違った傾向の下で、様々な方々に加わっていただけることは、正に言葉を身につけることに、年齢や状況の相違といった隔たりに、いかなる影響も受けないのだということを改めて実感しています。
そうした変化に後押しされながら、今回からまた英語を身につけることをテーマに書き綴っていきたいと考えます。先日、読売新聞の教育関連欄に興味深い記事を見つけました。それは、中学高校の英語教員の方々が、政府関連機関及び民間機関(例えば、British Council)が実施する「英語による英語教育プログラム」に積極的に参加を開始し始めているという趣旨のものでした。ある英語による英語教授法講座は、応募者が募集人員の数倍に達しているということです。民間機関慰よる講座は、1回の参加料金が10,000円をはるかに超えるにも関わらず、学校教員の方々が英語の運用力を高め現場で英語によるコミュニケーションを実践することは望ましいことです。
これまで、当教室では受験コースを含め英語による英語の授業をレベルに応じて実践して来ました。その中で、いつも気を付けなければならないと思うことはいくつかあります。以下、英語を英語で教授する際の当なりの注意事項です。
1.英語のどの部分を英語で教授するか。コミュニケーションスキル・文法・リーディング素材・エッセイライティング・スピーチまたはプレゼンテーション指導等、項目は多岐に渡るためその一つ一つについて素材を厳選し、教え方のシナリオと構成を考える必要があるということ。
2.英語で教授するための精緻な文法知識が必要となること。
3.自分自身が仕上げたシナリオを十分うまく生徒に伝わるように英語表現力をつけること。この際、特に動詞を中心とするCollocationに十分注意し間違った繋がり表現を教えないこと。
4.間違った発音をしないこと。つまり自分自身でネイティヴスピーカーが話す音を忠実に実現すること。同時に語の「ストレス(協調)」の位置を正確に声にして覚えること。例えば、theを「ザァ」などと決して発音しないことや、adviceを「アドヴァイス」などと日本語発音で発生しないこと等々。
以上の事項は、まだまだほんの一部で研鑽事項はこれらをはるかに超えますが、「英語を英語で教える」ことには、多大な知識と正確な運用力の習得が求められるということを忘れてはならないということです。そして何より大事なのは、無限の可能性を持つ10代の生徒達を英語で教えることには責任が伴うということです。彼らが間違った表現や発音で英語という言葉を身につけてしまうことに、ある意味緊張と恐怖感を持って臨むことは極めて重要です。
当教室の場合は、子供のみならず大人の方々に関しても、英語による教授方法には常に注意を払い臨んでいます。以前より通訳の訓練方法に関して表面的に言及して来ましたが、一部の私立高校などではそれらを英語の授業の中に導入しているようです。よく「シャドウイング」という言葉を耳にされる方々も多いかと思いますが、これは通訳者育成のための一つの訓練方です。別名「Follow」とも呼ばれています。こうした試みは悪いことではないと思いますが、この訓練法の本当の意味を知らず「ネイティヴスピーカーの話す音を、ただ影を追うように追いかけて音声を発するもの」などと間違った考えの基にて教えても何の効果もあがりません。Followに限らず、通訳の訓練法は、常に理解に裏付けされていなければならないということを忘れてしまっては、全く意味のない単なる「やった気分になる練習」で終わってしまいます。ましてや「聞き流し」などはモッテノホカです。
通訳の訓練方法の多くは、今後義務教育での英語教育に限らず、どんな学習者にとっても必要な要素を多く携えています。こうした方法を英語で教える事と融合させれば、中学高校、更には社会人の方々が正に必要としている英語力は習得可能であると考えます。
上記の内容に興味を持たれた方や現役の英語教員の方々の中で、ご自身の英語運用力を更に向上させたいとお考えの方はご遠慮なく連絡ください。政府関連機関、民間機関が提供している講座には限りがあり、まだ頻繁に実施されているわけではありません。当教室では、10年前の創設当初からこの種の講座を企画してきました。プライベイトでの対応、ワークショップ形式での講座実施に向け本格的に始動します。お問い合わせは以下まで。国際化の重大な一助となるべき英語を本気で教える、身につけることをそろそろ考えませんか。
次回は、昨春小学校を卒業して入室してきた男子生徒S太郎くん(市立中学校新中学2年生)の驚くべき英語上達の過去一年に触れながら、年齢に関係ない英語の上達方法も含め今回の話題を発展させていきます。
追伸: S太郎の授業は、この一年ほぼ英語のみで実施してきました。
◆お問い合わせ
「学べる英語教室」 Good Performer グッドパフォーマー
電話: 042-486-2004
e-mail: good-performer@jcom.home.ne.jp
URL: http://chofu.com/good-performer/ (ちょうふどっとこむポータルサイト)
早慶大及び国公立大学英語対策コース2016年春合格実績!
2016年03月17日
こんにちは。昨年7月より大学受験英語コースを発展させ、新たに設立した早慶大兼国公立大2次英語対策コースの本年度2015の合格実績を、再度お知らせします。
期間が短かったにも関わらず、3人という少人数で実施してきたこのコース、7ヶ月の間、生徒は皆とても前向きに取り組んでくれました。英語は当教室で学び、他の国語、社会、生物、化学などの科目は他の予備校または自習によって対応してきた3人の生徒たちです。3人の内2人は昨年2月より前に入室してくれていた生徒さんで、他の一人は昨年8月後半からの参加でした。結果は、まず一人目は、国立千葉大学理学部生物学科、上智大学理工学部物質生命理工学科、立教大学理学部生命理学科、明治大学理工学部電気電子生命学科という難関大学全てに合格し、昨年8月から参加してくれた生徒さんも英語の偏差値を47から63まで伸ばし明治大学情報コミュニケーション学部、成城大学、成蹊大学に合格を果たしてくれました。もう一人も極めて高い英語力を備えており、慶応義塾大学文学部を目指し力をすばらしく向上させてくれましたが明治学院大学法学部に進学を決めました。初回コースにおいては、早慶大合格者を出すことはできませんでしたが、学ぶという観点から言えば今回見事に現役合格してくれた3人の生徒に心から祝意と感謝の念を捧げたいと思うばかりです。
当教室は当初社会人・大学生の方々の学びの場としてスタートしましたが、若い世代の方々に一刻も早く言葉としての英語を身につけていただくことにも力を注がなければならないという思いから、中学生以上の生徒さんも学べる場として変貌してきました。この流れは、2021年以降始まる国際化に根差した教育改革を視野に入れ今後も持続していきます。そしてこのコースも進化させていきたいと思っています。
早稲田大学、慶応義塾大学は確かに優れた教育内容を誇る大学だと思います。国公立大学もターゲットとし日本の高等教育の本当の意味での質を高めるためにも、英語という観点から人材育成に尽力しようと改めて自戒の念に思いを馳せております。早慶大、国立大学という環境は、学問、人間性において更なる進歩を図りたいと思う若者達がそれを実現することをより高い確率で可能にしてくれる場であることを念頭に、今後もこのコースは継続していきます。但し、同時に忘れてはならないのは、いつも自分の立ち位置を見据え、将来自分が進む道を決め自信を持って邁進する事。それを実現する手段として、早慶大や国公立大学に入ることが必須条件とは限らないということを認識することもまた重要かもしれません。大事なのは、社会という環境の中で精一杯自分のできることを模索し、周囲に配慮し協力を得ながら、邁進することだと考えます。それは、自分の考え方次第でどんな環境においても可能なことなのではないでしょうか。これからも命の続く限り、微力ながら後方支援していきます。
次回は、また英語の学び方について戻り、大人・若者・子供を問わず言葉として学ぶ英語について社会での位置づけに言及しながらお伝えして参ります。この3ヶ月弱の間に溜まったことを早くおつたえしなければ・・・です。
期間が短かったにも関わらず、3人という少人数で実施してきたこのコース、7ヶ月の間、生徒は皆とても前向きに取り組んでくれました。英語は当教室で学び、他の国語、社会、生物、化学などの科目は他の予備校または自習によって対応してきた3人の生徒たちです。3人の内2人は昨年2月より前に入室してくれていた生徒さんで、他の一人は昨年8月後半からの参加でした。結果は、まず一人目は、国立千葉大学理学部生物学科、上智大学理工学部物質生命理工学科、立教大学理学部生命理学科、明治大学理工学部電気電子生命学科という難関大学全てに合格し、昨年8月から参加してくれた生徒さんも英語の偏差値を47から63まで伸ばし明治大学情報コミュニケーション学部、成城大学、成蹊大学に合格を果たしてくれました。もう一人も極めて高い英語力を備えており、慶応義塾大学文学部を目指し力をすばらしく向上させてくれましたが明治学院大学法学部に進学を決めました。初回コースにおいては、早慶大合格者を出すことはできませんでしたが、学ぶという観点から言えば今回見事に現役合格してくれた3人の生徒に心から祝意と感謝の念を捧げたいと思うばかりです。
当教室は当初社会人・大学生の方々の学びの場としてスタートしましたが、若い世代の方々に一刻も早く言葉としての英語を身につけていただくことにも力を注がなければならないという思いから、中学生以上の生徒さんも学べる場として変貌してきました。この流れは、2021年以降始まる国際化に根差した教育改革を視野に入れ今後も持続していきます。そしてこのコースも進化させていきたいと思っています。
早稲田大学、慶応義塾大学は確かに優れた教育内容を誇る大学だと思います。国公立大学もターゲットとし日本の高等教育の本当の意味での質を高めるためにも、英語という観点から人材育成に尽力しようと改めて自戒の念に思いを馳せております。早慶大、国立大学という環境は、学問、人間性において更なる進歩を図りたいと思う若者達がそれを実現することをより高い確率で可能にしてくれる場であることを念頭に、今後もこのコースは継続していきます。但し、同時に忘れてはならないのは、いつも自分の立ち位置を見据え、将来自分が進む道を決め自信を持って邁進する事。それを実現する手段として、早慶大や国公立大学に入ることが必須条件とは限らないということを認識することもまた重要かもしれません。大事なのは、社会という環境の中で精一杯自分のできることを模索し、周囲に配慮し協力を得ながら、邁進することだと考えます。それは、自分の考え方次第でどんな環境においても可能なことなのではないでしょうか。これからも命の続く限り、微力ながら後方支援していきます。
次回は、また英語の学び方について戻り、大人・若者・子供を問わず言葉として学ぶ英語について社会での位置づけに言及しながらお伝えして参ります。この3ヶ月弱の間に溜まったことを早くおつたえしなければ・・・です。
英語教員ワークショップの必要性!!
2015年09月19日
こんにちは。なんと前回投稿から3か月近くが過ぎてしまいました。何たる怠け者、でも同時に公私共に色々なことがありました。今年は、例年になく生徒さんの出入りが著しく、考えさせられることの多い3か月でした。今後は、量より質の記事作成を心掛けようと戒めています。
季節も夏との境目がよくわからないまま既に秋ですね。でも何かを始めるのに良い季節になったとも言えます。新たに始めることの一つに、英語学習を加えていただけましたら何よりです。
さて前回までの続きとして、大学入試改革の枠組みで新たに変わろうとしてしている英語教育について、少しだけお話しさせてください。現在、社会人と中学、高校生、更には大学生までの指導をさせていただく中で、やはり強く感じるのは中学、高校時代の英語教育の在り方であると痛感せざるを得ません。大人になって仕事等の必要性から、英語を新たに一から学び直さなければならないのは何故なのでしょうか。その答えは、これまでもお話ししてきた中学・高校の英語教育の中にあることが、最近殊に自分自身の中で明確になってきました。
大学入試改革の柱の一つである英語教育の転換は、ある意味好ましいことであるでしょう。英語を言葉として捉え運用力養成重視の内容へと変貌させる大義は、確かに方向性としては好ましいことなのかもしれません。ただそれを実現するために、日米の民間機関が実施する英語能力検査試験、例えば英検、TOEFL、IELTSの受験を積極的に進めることを学校側に促すことは、果たして妥当な判断なのでしょうか。試験そのものに問題があるというわけではなく、それらを導入するために準備段階として何が必要なのかを考え、体制を確立することが大切なのではという思いをいつもながら強く感じます。
当方の教室のある高校1年生の学校(都立高校)では、英語コミュニケーションの授業を日本人の教員が授業のうちかなりの割合で英語によって説明・指導しているそうです。教科書の内容をコンピューターデータに落とし、プロジェクターを使ってスクリーンに映し出して内容説明するそうですが、ほとんどの生徒がそれまでこうした形態の授業経験がないため困惑するばかりで身につくものが極めて少ないようです。試みとしては、先進的要素があり悪い事ではないにしても、言葉を学ぶには段階があることを認識して実践することもまた必要なことです。
高校でこうした授業をいきなり実施するのではなく、中学校の初めの時期に聞く、読む、文法をバランスよく組み合わせた統合型授業を実践し、中学3年から英語を話す練習を始め、高校で英語のみの授業を実施していくというような一連の繋がりが不可欠に思えてなりません。
もう一つ重要なことは、前にもお伝えしましたように教える側の技術向上を図ること。上記の学校の日本人教員の方は無論英語の口頭能力向上のための努力をされた後に授業を担当されているのだとは思いますが、どうも英語表現、特にワードチョイス、発音に多少の問題があるのも事実なようです。これは個々の教師の方々の力量に学校側が任せすぎるから起こることで、ご本人に全て責任がある訳ではないと思います。今、学校側という言葉を使いましたが、それは敢えて言えば文科省のことであり、文科省が建前的な英語教育改革ではなく教員の方々の研修制度を拡充させ土台から築きあげていくことの必要性を意味するものです。
TOEFLやIELTSを本当に日本の大学までの英語教育に何らかの形で導入するのであれば、上記の対応は一刻も早く着手することが肝要であると感じます。当教室でも新たなプランを模索中です。それは、中学高校の教員の方々と行う英語教授のためのワークショップです。教員の方々の英語力向上と英語による教授法を共に学べる機会を、今後設けることを計画してみようと思っています。
身近にこうしたワークショップに興味のあられる教員の方がいらしたら、是非こんな計画があることお伝えいただけますでしょうか。微力ながら共に成長していくための行動を開始してみようと思います。
季節も夏との境目がよくわからないまま既に秋ですね。でも何かを始めるのに良い季節になったとも言えます。新たに始めることの一つに、英語学習を加えていただけましたら何よりです。
さて前回までの続きとして、大学入試改革の枠組みで新たに変わろうとしてしている英語教育について、少しだけお話しさせてください。現在、社会人と中学、高校生、更には大学生までの指導をさせていただく中で、やはり強く感じるのは中学、高校時代の英語教育の在り方であると痛感せざるを得ません。大人になって仕事等の必要性から、英語を新たに一から学び直さなければならないのは何故なのでしょうか。その答えは、これまでもお話ししてきた中学・高校の英語教育の中にあることが、最近殊に自分自身の中で明確になってきました。
大学入試改革の柱の一つである英語教育の転換は、ある意味好ましいことであるでしょう。英語を言葉として捉え運用力養成重視の内容へと変貌させる大義は、確かに方向性としては好ましいことなのかもしれません。ただそれを実現するために、日米の民間機関が実施する英語能力検査試験、例えば英検、TOEFL、IELTSの受験を積極的に進めることを学校側に促すことは、果たして妥当な判断なのでしょうか。試験そのものに問題があるというわけではなく、それらを導入するために準備段階として何が必要なのかを考え、体制を確立することが大切なのではという思いをいつもながら強く感じます。
当方の教室のある高校1年生の学校(都立高校)では、英語コミュニケーションの授業を日本人の教員が授業のうちかなりの割合で英語によって説明・指導しているそうです。教科書の内容をコンピューターデータに落とし、プロジェクターを使ってスクリーンに映し出して内容説明するそうですが、ほとんどの生徒がそれまでこうした形態の授業経験がないため困惑するばかりで身につくものが極めて少ないようです。試みとしては、先進的要素があり悪い事ではないにしても、言葉を学ぶには段階があることを認識して実践することもまた必要なことです。
高校でこうした授業をいきなり実施するのではなく、中学校の初めの時期に聞く、読む、文法をバランスよく組み合わせた統合型授業を実践し、中学3年から英語を話す練習を始め、高校で英語のみの授業を実施していくというような一連の繋がりが不可欠に思えてなりません。
もう一つ重要なことは、前にもお伝えしましたように教える側の技術向上を図ること。上記の学校の日本人教員の方は無論英語の口頭能力向上のための努力をされた後に授業を担当されているのだとは思いますが、どうも英語表現、特にワードチョイス、発音に多少の問題があるのも事実なようです。これは個々の教師の方々の力量に学校側が任せすぎるから起こることで、ご本人に全て責任がある訳ではないと思います。今、学校側という言葉を使いましたが、それは敢えて言えば文科省のことであり、文科省が建前的な英語教育改革ではなく教員の方々の研修制度を拡充させ土台から築きあげていくことの必要性を意味するものです。
TOEFLやIELTSを本当に日本の大学までの英語教育に何らかの形で導入するのであれば、上記の対応は一刻も早く着手することが肝要であると感じます。当教室でも新たなプランを模索中です。それは、中学高校の教員の方々と行う英語教授のためのワークショップです。教員の方々の英語力向上と英語による教授法を共に学べる機会を、今後設けることを計画してみようと思っています。
身近にこうしたワークショップに興味のあられる教員の方がいらしたら、是非こんな計画があることお伝えいただけますでしょうか。微力ながら共に成長していくための行動を開始してみようと思います。
現英語教育と制度改革のギャップって?
2015年05月10日
こんにちは。季節がまた変わり目を迎える時期になってきましたね。春から夏へ活動的に振る舞える季節でもありますが、猛暑、地震、気候変動など不安や懸念が再燃しやすい時期でもあります。いつも気を緩めず(たまには緩めたいですが…)、自他に気を配り淡々と日々を送ることが一番良いのかもしれません。
今回は、前回お話しした大学入試改革の一つの柱である英語教育の運用力重視への方向転換に加えて、それに続く大学の在り方についても考えてみたいと思います。最終段階では、年齢に関係なく英語を言葉としてどのように学ぶことが望ましいのか、モデルメソッドやカリキュラムについての企画提案も考えたいと思っています。この一連の内容は、今回のみの投稿ではとても語り切れないですから、何回かに分けてお伝えして行きます。
前回お話しました中央教育審議会の大学入試への英語スピーキング&ライティング力を評価する民間機関による試験導入を促すという答申につき、実現する上での優先事項をお伝えしました。
「国際化の促進」とうことばに焦点を絞りすぎて、それを形にするプロセスを怠ることは教育現場に様々な歪を生じることになります。先ずはその大義を支える教育者人材の育成を優先することの必要性を記しました。では何故それが重要なのでしょうか。
皆さんの中には、例えばTOEFLとう試験が現在どんな内容で、どんな実施のされ方をしているかご存じの方々も多いかと思います。この試験は、現在のTOEICタイプのPBT(Paper Based Test)の形態で実施開始され、主に米国豪州を中心とする英語圏の大学と大学院入学に求められる英語力を検査する試験として定着してきました。現在ではiBT (Internet Based Test)という形体で実施されています。これは、onlineでコンピューターの前にHeadsetを装着し、リーディング・リスニング・スピーキング・ライティングすべての英語技能が、コンピューターディスプレイ及び音声の指示に従って解答することで審査される試験です。
出題される英語のトピックは、高等教育機関(大学、大学院)で扱われる様々な学問分野から出題され、極めてレベルの高い語彙・表現が含まれます。中でもライティングとスピーキングは、特定分野の大学での講義・学生と教授のディスカッション・キャンパスでの学生同士の大学の教育方針に関する会話等を音声で聞き取り、それを基に英語で要約するもの、講義内容の論点の説明、対峙する意見の対比説明等を決められた時間内で、かつ決められた語数で解答していくという問題が主流となります。スピーキングはマイクに向かって話すことで録音され、ライティングはキーボードにタイプして解答を作成します。メモ取りは自由です。メモ用紙は配布されます。また特定のトピックに従って、同じく決められた時間内、語数で解答を校正し話す、書くことも別のセクションで求められます。トータルで4時間、受ける試験によっては、フェイクの問題が追加されていてトータルで4時間30分以上になることもあります。各技能30点配点、満点120点のテストです。
TOEFLは、今や最も手強い英語の試験になっていますが、英国の大学、大学院に入学するために必要なIELTSとい試験も4つの技能を検査する難解な試験です。中教審を屋台骨とする文科省は、この2つの試験も含めて日本の大学入試への導入を推進しているわけです。そこで質問です。こうした試験対策を全国規模で誰が指導するのでしょうか。現役の中学高校の先生方に自己研鑽していただいて指導することを、まさか考えているとは思えません。というよりそれはかなり無謀なことと考えます。だからこそこうした試験を導入するのであれば、指導する側の研修育成が必要となる訳です。
文科省の大学入試改革の中の海外英語教育機関を含めた民間試験の導入促進について、もう少し調べて次回は投稿します。
今回は、前回お話しした大学入試改革の一つの柱である英語教育の運用力重視への方向転換に加えて、それに続く大学の在り方についても考えてみたいと思います。最終段階では、年齢に関係なく英語を言葉としてどのように学ぶことが望ましいのか、モデルメソッドやカリキュラムについての企画提案も考えたいと思っています。この一連の内容は、今回のみの投稿ではとても語り切れないですから、何回かに分けてお伝えして行きます。
前回お話しました中央教育審議会の大学入試への英語スピーキング&ライティング力を評価する民間機関による試験導入を促すという答申につき、実現する上での優先事項をお伝えしました。
「国際化の促進」とうことばに焦点を絞りすぎて、それを形にするプロセスを怠ることは教育現場に様々な歪を生じることになります。先ずはその大義を支える教育者人材の育成を優先することの必要性を記しました。では何故それが重要なのでしょうか。
皆さんの中には、例えばTOEFLとう試験が現在どんな内容で、どんな実施のされ方をしているかご存じの方々も多いかと思います。この試験は、現在のTOEICタイプのPBT(Paper Based Test)の形態で実施開始され、主に米国豪州を中心とする英語圏の大学と大学院入学に求められる英語力を検査する試験として定着してきました。現在ではiBT (Internet Based Test)という形体で実施されています。これは、onlineでコンピューターの前にHeadsetを装着し、リーディング・リスニング・スピーキング・ライティングすべての英語技能が、コンピューターディスプレイ及び音声の指示に従って解答することで審査される試験です。
出題される英語のトピックは、高等教育機関(大学、大学院)で扱われる様々な学問分野から出題され、極めてレベルの高い語彙・表現が含まれます。中でもライティングとスピーキングは、特定分野の大学での講義・学生と教授のディスカッション・キャンパスでの学生同士の大学の教育方針に関する会話等を音声で聞き取り、それを基に英語で要約するもの、講義内容の論点の説明、対峙する意見の対比説明等を決められた時間内で、かつ決められた語数で解答していくという問題が主流となります。スピーキングはマイクに向かって話すことで録音され、ライティングはキーボードにタイプして解答を作成します。メモ取りは自由です。メモ用紙は配布されます。また特定のトピックに従って、同じく決められた時間内、語数で解答を校正し話す、書くことも別のセクションで求められます。トータルで4時間、受ける試験によっては、フェイクの問題が追加されていてトータルで4時間30分以上になることもあります。各技能30点配点、満点120点のテストです。
TOEFLは、今や最も手強い英語の試験になっていますが、英国の大学、大学院に入学するために必要なIELTSとい試験も4つの技能を検査する難解な試験です。中教審を屋台骨とする文科省は、この2つの試験も含めて日本の大学入試への導入を推進しているわけです。そこで質問です。こうした試験対策を全国規模で誰が指導するのでしょうか。現役の中学高校の先生方に自己研鑽していただいて指導することを、まさか考えているとは思えません。というよりそれはかなり無謀なことと考えます。だからこそこうした試験を導入するのであれば、指導する側の研修育成が必要となる訳です。
文科省の大学入試改革の中の海外英語教育機関を含めた民間試験の導入促進について、もう少し調べて次回は投稿します。
英語教育改革の道のりは? 英語教室GP
2015年04月14日
こんにちは。4月に入り冷たい雨が続いていましたが、ようやく春めいた新緑の季がやってきましたね。春から初夏に向けて気候の変化と共に教室でも様々な変化が起こりつつあります。いいこと悪いことを問わず無変化に甘んじることなく変化を追及していきたいものです。
前回お伝えしましたように、今回は国際化を目指す日本の英語教育改革審議について思うことを綴らせていただければと考えます。かなり前になりますが、今年2月21日付読売新聞に「変わる大学入試」と題した記事が掲載されましたね。改革の柱の一つである英語試験に関する新しい試みに対して深い興味を持ちました。文科省の教育改革の核的組織中央教育審議会は、各大学に英検・IELTS・TOEFLといった内外民間機関が実施する英語試験を積極的に一般試験に取り入れることを促していくとのこと。目的は、これまでの読む・訳す・単語を暗記する・文法主体の学習にメスを入れるということのようです。つまり話す・書く・読む・聞くという言葉本来の役割にフォーカスした本来実施すべき言葉の学習方法を中高教育の中に実現させていくことが狙いのようです。
こうした改革は、基本的には望ましいものと考えます。ただ本来英語は言葉なのだから、国境を越えたコミュニケーションを実現するために習得すべきことは当然のことで、なぜもっと早い時期に・・・という思いも同時に働きます。当教室は、「英語は言葉、使えなければ意味がないもの。」というモットーに基づいて、学ぶ場を提供実施してきました。この思いは、ある意味「当然なのに何故正規義務教育または民間の教育組織団体の中で実践されていないのだろうか。」という疑問から始まったものです。今後もこうした教育改革が進む進まないに限らず、持続していくことの重要性を改めて認識する機会なのではないかと受け止めています。
ところで、もしこの方向性が実現に向けて進んで行くとして、最優先して形にしていかなければならないこととは一体どんなことなのでしょうか。実践的カリキュラムの考案、言葉に対する意識改革、学習環境設備の拡充、どれも重要ですね。しかし何より大切なことは、改革の重要性に対する教育する側の強い認識と教授技術の向上にあると考えます。どんな事柄や問題に対しても、大義を唱えることはある意味易しいことです。ではその大義をどんなプロセスで実施していくのか、またそのために必要な要素は何か、更にはその必要な要素をどう形にし生み出していくのかの方法論無しでは、見た目の良い空箱のまま終わってしまいます。大義・目標を達成するための土台となるものをしっかりと思考し具体的な方策を完成させることが、今最も大切な事なのではないでしょうか。
教育制度下にある若い世代の国際化を意図して言語教育の改革を目指すのであれば、まず教育に従事する者の力量をもっともっと向上させなければなりません。そのために文科省を中心とする行政側が、しっかりとした予算形成をして教える側の人材育成を中心とした仕組み作りに一刻も早く着手すべきかと考えます。
次回は、英語教育の改革について、新聞記事にあったTOEFLなどの英語試験の仕組み・利点とその試験の持つ意味と対策に言及しながら必要なことをもう少し掘り下げて考えてみようと思います。
前回お伝えしましたように、今回は国際化を目指す日本の英語教育改革審議について思うことを綴らせていただければと考えます。かなり前になりますが、今年2月21日付読売新聞に「変わる大学入試」と題した記事が掲載されましたね。改革の柱の一つである英語試験に関する新しい試みに対して深い興味を持ちました。文科省の教育改革の核的組織中央教育審議会は、各大学に英検・IELTS・TOEFLといった内外民間機関が実施する英語試験を積極的に一般試験に取り入れることを促していくとのこと。目的は、これまでの読む・訳す・単語を暗記する・文法主体の学習にメスを入れるということのようです。つまり話す・書く・読む・聞くという言葉本来の役割にフォーカスした本来実施すべき言葉の学習方法を中高教育の中に実現させていくことが狙いのようです。
こうした改革は、基本的には望ましいものと考えます。ただ本来英語は言葉なのだから、国境を越えたコミュニケーションを実現するために習得すべきことは当然のことで、なぜもっと早い時期に・・・という思いも同時に働きます。当教室は、「英語は言葉、使えなければ意味がないもの。」というモットーに基づいて、学ぶ場を提供実施してきました。この思いは、ある意味「当然なのに何故正規義務教育または民間の教育組織団体の中で実践されていないのだろうか。」という疑問から始まったものです。今後もこうした教育改革が進む進まないに限らず、持続していくことの重要性を改めて認識する機会なのではないかと受け止めています。
ところで、もしこの方向性が実現に向けて進んで行くとして、最優先して形にしていかなければならないこととは一体どんなことなのでしょうか。実践的カリキュラムの考案、言葉に対する意識改革、学習環境設備の拡充、どれも重要ですね。しかし何より大切なことは、改革の重要性に対する教育する側の強い認識と教授技術の向上にあると考えます。どんな事柄や問題に対しても、大義を唱えることはある意味易しいことです。ではその大義をどんなプロセスで実施していくのか、またそのために必要な要素は何か、更にはその必要な要素をどう形にし生み出していくのかの方法論無しでは、見た目の良い空箱のまま終わってしまいます。大義・目標を達成するための土台となるものをしっかりと思考し具体的な方策を完成させることが、今最も大切な事なのではないでしょうか。
教育制度下にある若い世代の国際化を意図して言語教育の改革を目指すのであれば、まず教育に従事する者の力量をもっともっと向上させなければなりません。そのために文科省を中心とする行政側が、しっかりとした予算形成をして教える側の人材育成を中心とした仕組み作りに一刻も早く着手すべきかと考えます。
次回は、英語教育の改革について、新聞記事にあったTOEFLなどの英語試験の仕組み・利点とその試験の持つ意味と対策に言及しながら必要なことをもう少し掘り下げて考えてみようと思います。
英語の力って? 英語を言葉として身に付けよう!!
2015年03月15日
こんにちは。前回からまたまた間が空いてしまいました。気が付けばもう3月も終わり。桜の花見ができるのは楽しみだけど、なんだか時の流れの速さに圧倒されてしまいます。早くやらなければならないこと開始しなければ、と焦り気味になっている近頃です。
本格的な春に近づきつつある今の時期、英語学習を取り巻く環境でよく聞かれる「簡単、英語の学び方」「英語は聞き流して話せるようになりますよ。」「3か月で英語が流暢に話せる方法あり」などなど、魅力的な言葉が飛び交っていますね。ふむふむ、そうした方法が本当にあるならば、日本全国英語を巧みに操るひとばかりのはずですね。ところが周知のごとく、しっかりした英語力でコミュニケーションできる人は実に少なく、こつこつと日々英語と携わることで知識を蓄えながら習得している方々を目にするだけに止まっています。
以前からお伝えしている「英語の学び方」に関する洞察、再開したいと考えます。英語はそもそも使うもの、広範な人間関係を作り上げたり、仕事をスムーズに進めたりすることを実現するための手段です。つまり勉強、学習という言葉とはややかけ離れたところに位置する技能です。机に向かって電子辞書を使って学ぶようなものでもなく、また反面楽に思考力を無視して五感が感じるままのものを素通りさせて身に付くものでもありません。
日本人誰もが、学校教育に始まり、マスメディアや実際に身近に存在する外国人から英語という言語に触れることは経験してきたはずです。その基盤があれば、後は勉強ではなく行動をするだけで十分です。まずは何より聞くことから始めることです。但し聞き流しはだめです。英語は、使う文字、ルール、作り、語の形態、組み立て方、そして何より発音・ストレスが基本的に日本語と異なります。1000回聞いても分からないないものは分かりません。それに日本語の訳づけをしたからと言って何一つ大きな違いはありません。とにかく僅かでも一向にかまいません、現在身についている知識を基に一つのまとまった英語を聞いて目いっぱい意味を取る努力をすること、そして例えたどたどしくても、いやたった一単語ででもいいから、聞いた英語の内容について英語で描写する努力、つまり話すことを試みることが何よりも大切です。
そして次のステップは・・・。そこからは聞いた内容をルールに従って語の訴えている意味をしっかり汲み取って、しっかり詳細チェックをすること、そして終着点として自分が表現した最初の英語を洗練した英語へと仕上げていくことです。このプロセスを様々なタイプの英語を聞きながら、辛坊強く一定期間続けることが言葉としての英語を完成させる一番の近道の一つです。
次回は、先日マスメディアで公表された、文科省による大学入試への民間英語試験の導入奨励答申の話を交えながら「言葉としての英語」へのアプローチについてお話しします。間隔をあけないように頑張ります!!
本格的な春に近づきつつある今の時期、英語学習を取り巻く環境でよく聞かれる「簡単、英語の学び方」「英語は聞き流して話せるようになりますよ。」「3か月で英語が流暢に話せる方法あり」などなど、魅力的な言葉が飛び交っていますね。ふむふむ、そうした方法が本当にあるならば、日本全国英語を巧みに操るひとばかりのはずですね。ところが周知のごとく、しっかりした英語力でコミュニケーションできる人は実に少なく、こつこつと日々英語と携わることで知識を蓄えながら習得している方々を目にするだけに止まっています。
以前からお伝えしている「英語の学び方」に関する洞察、再開したいと考えます。英語はそもそも使うもの、広範な人間関係を作り上げたり、仕事をスムーズに進めたりすることを実現するための手段です。つまり勉強、学習という言葉とはややかけ離れたところに位置する技能です。机に向かって電子辞書を使って学ぶようなものでもなく、また反面楽に思考力を無視して五感が感じるままのものを素通りさせて身に付くものでもありません。
日本人誰もが、学校教育に始まり、マスメディアや実際に身近に存在する外国人から英語という言語に触れることは経験してきたはずです。その基盤があれば、後は勉強ではなく行動をするだけで十分です。まずは何より聞くことから始めることです。但し聞き流しはだめです。英語は、使う文字、ルール、作り、語の形態、組み立て方、そして何より発音・ストレスが基本的に日本語と異なります。1000回聞いても分からないないものは分かりません。それに日本語の訳づけをしたからと言って何一つ大きな違いはありません。とにかく僅かでも一向にかまいません、現在身についている知識を基に一つのまとまった英語を聞いて目いっぱい意味を取る努力をすること、そして例えたどたどしくても、いやたった一単語ででもいいから、聞いた英語の内容について英語で描写する努力、つまり話すことを試みることが何よりも大切です。
そして次のステップは・・・。そこからは聞いた内容をルールに従って語の訴えている意味をしっかり汲み取って、しっかり詳細チェックをすること、そして終着点として自分が表現した最初の英語を洗練した英語へと仕上げていくことです。このプロセスを様々なタイプの英語を聞きながら、辛坊強く一定期間続けることが言葉としての英語を完成させる一番の近道の一つです。
次回は、先日マスメディアで公表された、文科省による大学入試への民間英語試験の導入奨励答申の話を交えながら「言葉としての英語」へのアプローチについてお話しします。間隔をあけないように頑張ります!!
英語教育はどこへ? PartⅡ
2014年11月25日
こんにちは。またまた久しぶりの投稿で失礼します。今年もあと1か月余り、当方の仕事の種類がやや多様化してきており、仕事の取捨選択が必要なことを感じています。来年に向けて、英語の指導方法を集大成していく必要性がありそうです。
さて前回までの「今後の英語教育の行方?」について、今回から新しいタイプの英語教育に着手する際のプロセスを段階的に述べていきたいと思います。これは「論文」ではありませんから、教室で起こったことや、当方が指導しながら感じたことを織り込みながらお伝えしていきます。
先週、紙面上で文科省の英語教育に関する答申原案が公開されましたね。小学校3年生からの英語教育導入、小学5、6年生での英語正式科目認定、中学段階での英語による授業の実施、そして高校段階での英語の運用力(討論、発表能力)養成の実施が、この7年以内に答申されるようですね。率直に言って、これはどの程度の実現可能性と、仮に開始したとして効果が上がるものなのでしょうか。
誰が、カリキュラムを開発し、誰がそれを現場で実施するのか、そのプランとプロセス、それに手法を明確にして公表しない限り、いわゆる机上の戯言としてしか耳に入ってきません。また他の教育内容との整合を図らず実施することは、大きなリスクを伴います。何か国際化・グローバル化という言葉に踊らされて、焦りの中で表明された案でしかないように感じ賛同に値するものとは到底言えません。
このことは本ブログの目指すところと相舞うところが多く、別枠で議論を展開したいと思っています。以前からお伝えしているように、英語教育は英語を外国語として実際に学び国内海外を問わず、英語のみを使う環境の中でその習得を果たした人材が担うべきだと考えています。加えて指導するための技術と知識を求められることは言うまでもありません。英語を英語で全国規模で教える…? 「誰が?」という疑問を持たざるをえません。英語にはいや言語には守らなければならないルールがあります。時にそれは、英語で英語でを教えることであり、また実際にそれが言葉として現実の社会で使われることを常に念頭に置き、1回1回の授業を指導することでもあります。
当教室では、まさに実際にそれを実施しています。その内容って…? 文科省答申の内容は、何も義務教育に限って議論するものではなく、英語を言葉として身に付けるために実現していくべき道と関連付けて考える必要があるようです。英語教育の改革を目指すなら、教員の研修制度、教材の抜本的見直し、実践性あるカリキュラムの開発など、体制を整える指針と人材確保の見込みと計画が整ってから進めるべきだと感じてなりません。
さて前回までの「今後の英語教育の行方?」について、今回から新しいタイプの英語教育に着手する際のプロセスを段階的に述べていきたいと思います。これは「論文」ではありませんから、教室で起こったことや、当方が指導しながら感じたことを織り込みながらお伝えしていきます。
先週、紙面上で文科省の英語教育に関する答申原案が公開されましたね。小学校3年生からの英語教育導入、小学5、6年生での英語正式科目認定、中学段階での英語による授業の実施、そして高校段階での英語の運用力(討論、発表能力)養成の実施が、この7年以内に答申されるようですね。率直に言って、これはどの程度の実現可能性と、仮に開始したとして効果が上がるものなのでしょうか。
誰が、カリキュラムを開発し、誰がそれを現場で実施するのか、そのプランとプロセス、それに手法を明確にして公表しない限り、いわゆる机上の戯言としてしか耳に入ってきません。また他の教育内容との整合を図らず実施することは、大きなリスクを伴います。何か国際化・グローバル化という言葉に踊らされて、焦りの中で表明された案でしかないように感じ賛同に値するものとは到底言えません。
このことは本ブログの目指すところと相舞うところが多く、別枠で議論を展開したいと思っています。以前からお伝えしているように、英語教育は英語を外国語として実際に学び国内海外を問わず、英語のみを使う環境の中でその習得を果たした人材が担うべきだと考えています。加えて指導するための技術と知識を求められることは言うまでもありません。英語を英語で全国規模で教える…? 「誰が?」という疑問を持たざるをえません。英語にはいや言語には守らなければならないルールがあります。時にそれは、英語で英語でを教えることであり、また実際にそれが言葉として現実の社会で使われることを常に念頭に置き、1回1回の授業を指導することでもあります。
当教室では、まさに実際にそれを実施しています。その内容って…? 文科省答申の内容は、何も義務教育に限って議論するものではなく、英語を言葉として身に付けるために実現していくべき道と関連付けて考える必要があるようです。英語教育の改革を目指すなら、教員の研修制度、教材の抜本的見直し、実践性あるカリキュラムの開発など、体制を整える指針と人材確保の見込みと計画が整ってから進めるべきだと感じてなりません。
英語教育は何処へ・・・? 英語教室GP
2014年10月21日
こんにちは。10月に入ってすっかり秋めいてきたのはよいですが、週初の2度に渡る台風には少々懸念を禁じえませんでした。また気が付くと10月も下旬へと向かい、改めて時の流れの速さを感じます。今年も早残り2ヶ月余りとは、既に年末の雰囲気が漂ってきましたね。そんな中、気の焦りからか自分のやるべきことをさっさと形にしなければと戒めているところです。
久々の投稿ですので、それまでお伝えしてきたことと重複させながら引き続き英語の効果的な学び方についてお話ししていきます。同時に前回、前々回と、これまで教室で起こったことに触れながら英語指導について考えをお伝えして来ましたが、今回は再度原点に帰って考えてみたいと思います。
特に最近、教室の大人の生徒さん達とよく話すことは、中学高校6年間、現在では小学校からの英語教育を含めれば7、8年は英語に触れ指導を受けているはずなのに、高校卒業時点でなぜ日常会話レベルの力すらも習得できないのかということ。いくら日本の環境だからといって、6年以上語学を学んだら言葉としての運用力は身について当たり前ですね。現在の英語教育、とにかく見直す時期に来ています。
中等教育の中で運用力が身につかない現実には、2つの大きな要因があると考えます。
1つは、言うまでもなく義務教育から高校までの英語指導方法とその基盤となるカリキュラム(教育課程)、そして他の一つは、大学受験から始まる大学教育の中での英語の位置づけです。前者に関しては、これまで何回も同じことを繰り返して述べてきた気がします。最も効果的な解決策は、英語を聞きながら、又は読みながらそのルールと表現を同時に習得できる指導方法を取り入れることと、それを実践するために語学力発達プロセスに長けた指導者による教育課程と教材の作りこみを実現することです。
そして後者に関しては、現在の大学受験英語から脱却して、運用力ベースの試験変更する必要があります。現在の大学受験英語の代替となる最も有力な試験は、何といってもTOEFLタイプの総合力判断試験でしょう。これを実践するためには、何も米国のETS (Educational Testing Service )に依存する必要はありません。大学には、それぞれ独自の考え方、強味、方向性があります。しかし高等教育の担うべき共通した責任は、学生達が社会に出た時、現実の厳しさに折れないような専門かつ実践的学問と知識の習得を実現することと、様々な環境の中で柔軟に対応できる考え方や思考力を要請することにあります。そのためには、世界という枠組みをしっかりと見据え、本当の意味での国際化を図る道を避けては通れません。各大学の独自性の中に真の国際化の種子とも言える言語としての英語を含めていくこともまた必要不可欠な要素です。
こうした英語に関する中等教育と高等教育の内容に整合性を見出して行く時、中高6年間の英語教育は画期的に変化することでしょう。
ではまず何から、どこから着手して行ったらよいのか、次回以降考えをお伝えしていきます。但し、途中でコーヒーブレイクも入れていきますが。。。
久々の投稿ですので、それまでお伝えしてきたことと重複させながら引き続き英語の効果的な学び方についてお話ししていきます。同時に前回、前々回と、これまで教室で起こったことに触れながら英語指導について考えをお伝えして来ましたが、今回は再度原点に帰って考えてみたいと思います。
特に最近、教室の大人の生徒さん達とよく話すことは、中学高校6年間、現在では小学校からの英語教育を含めれば7、8年は英語に触れ指導を受けているはずなのに、高校卒業時点でなぜ日常会話レベルの力すらも習得できないのかということ。いくら日本の環境だからといって、6年以上語学を学んだら言葉としての運用力は身について当たり前ですね。現在の英語教育、とにかく見直す時期に来ています。
中等教育の中で運用力が身につかない現実には、2つの大きな要因があると考えます。
1つは、言うまでもなく義務教育から高校までの英語指導方法とその基盤となるカリキュラム(教育課程)、そして他の一つは、大学受験から始まる大学教育の中での英語の位置づけです。前者に関しては、これまで何回も同じことを繰り返して述べてきた気がします。最も効果的な解決策は、英語を聞きながら、又は読みながらそのルールと表現を同時に習得できる指導方法を取り入れることと、それを実践するために語学力発達プロセスに長けた指導者による教育課程と教材の作りこみを実現することです。
そして後者に関しては、現在の大学受験英語から脱却して、運用力ベースの試験変更する必要があります。現在の大学受験英語の代替となる最も有力な試験は、何といってもTOEFLタイプの総合力判断試験でしょう。これを実践するためには、何も米国のETS (Educational Testing Service )に依存する必要はありません。大学には、それぞれ独自の考え方、強味、方向性があります。しかし高等教育の担うべき共通した責任は、学生達が社会に出た時、現実の厳しさに折れないような専門かつ実践的学問と知識の習得を実現することと、様々な環境の中で柔軟に対応できる考え方や思考力を要請することにあります。そのためには、世界という枠組みをしっかりと見据え、本当の意味での国際化を図る道を避けては通れません。各大学の独自性の中に真の国際化の種子とも言える言語としての英語を含めていくこともまた必要不可欠な要素です。
こうした英語に関する中等教育と高等教育の内容に整合性を見出して行く時、中高6年間の英語教育は画期的に変化することでしょう。
ではまず何から、どこから着手して行ったらよいのか、次回以降考えをお伝えしていきます。但し、途中でコーヒーブレイクも入れていきますが。。。
英語を学ぶ方々へ! 英語の教え方は?
2014年07月22日
7月も下旬、直ぐに真夏の波が押し寄せますね。今年の梅雨ようやく明けたようですね。今年は梅雨明けがやや遅く夏が短くなるのはちょっと寂しいですが、夏の酷暑を想像するとそれもまたありがたいことなのかもしれません。いずれにしろ天候が不順なのは気になりますね。
つい最近、英語教師の方に問い合わせをいただき、以前より考えていたことが頭の中で再起してきました。前回からの流れに加えて今日は、中学高校の英語教育にも触れながら英語指導について少しだけお話します。
当教師開設当初、中学高校の教員の方々対象に英語研修講座を開設したことがあります。きっかけは、公立中学の教員中途採用試験の二次面接試験の対策をしてほしいというご要望のメールでした。その方の要望は、一次試験は通過されましたが、二次の英語による口頭試験突破にどうしても自信が持てず対策を考えてほしいというものでした。当時、英検準1級、TOEIC800点を同時に目指されて勉強されていましたが、どうしても英語を話し書く力が向上せず悩まれていました。いくつかの英語学校に2年ほど通った後のことでした。当教室で秋の教員採用二次面接試験対策、英検、TOEIC対策の勉強を開始されたのは、7年前の6月のことでした。
過去問題をベースにした二次試験予想問題を作成し教員試験に備えると共にTOEIC対策、英検のライティング問題及び二次試験対策と盛りだくさんの内容で、週2回1回3時間に渡る勉強を開始したのです。準備をする中で、ご自身が学んできた英語と当教室の英語指導の内容とのギャップに驚嘆されることしばしばでした。仮定表現の多様さ、現在形の持つ意味、collocation(繋がり表現)の大切さ、英語の表現ベースでのくくり方、等々様々な内容を入れ込んで、ご本人が教壇に立たれることを前提に授業を進めました。無論、教員試験二次対策は、過去問から予想問題を作成しシュミレーション中心の授業を組み立てました。
結果は、教員採用二次英語面接試験合格、英検準1級合格、TOEIC785点取得という素晴らしいものでした。これは目標を達成したいという学習者の心の強さと、英語には学び方があるのだということを認識させてくれるものでした。
この生徒さんは、今23区内の公立中学で教鞭をとっています。このことをきっかけに中学高校教員研修講座を開設したのですが、その後はこの講座に対する問い合わせもほとんどなく、5年近い月日が流れてしまいました。ところがつい先日、ある中学の英語教諭の方あらメールをいただきました。メールの大まかな趣旨は、英語の文法・語彙・リスニングと包括的にご自身の力を不安に感じられ、再度勉強し直したいというものでした。こうした教師の方々がいることを再認識すると同時に、この教諭の方のお力になりたいと強く思いました。人は、日々仕事をこなしながら過ごしていると、敢えて自分自身と取り巻く環境の中で本当にやらなくてはならないことを考える機会を見失いがちになります。この先生は、敢えてご自身の将来と現状を照らし合わせ、今やらなくてはならないことを見出されたのだと感慨に浸りました。現在はまだメールでのやりとりで行動を開始する時期を模索中ですが、指導することを念頭にした教材を更に充実したものにするため開発に着手したところです。義務教育内で行われている英語教育を言葉としてより実用的なものに変容させるためには、こうした教員の方々の双肩に掛かっていると言ってもよいかもしれません。正し、それには行政側の理解と支援が不可欠であることもまた事実であると考えます。
年内から来年にかけこの「中学高校英語教員研修講座」を新たな講座としてスタートさせようと思案中です。
今回は、最近の出来事と英語を指導すること関連についてお話しするだけで、長くなってしまいました。次回は、このことも踏まえて、前回までの話に軌道修正し「英語の語学感覚と指導姿勢」についてお話しします。
つい最近、英語教師の方に問い合わせをいただき、以前より考えていたことが頭の中で再起してきました。前回からの流れに加えて今日は、中学高校の英語教育にも触れながら英語指導について少しだけお話します。
当教師開設当初、中学高校の教員の方々対象に英語研修講座を開設したことがあります。きっかけは、公立中学の教員中途採用試験の二次面接試験の対策をしてほしいというご要望のメールでした。その方の要望は、一次試験は通過されましたが、二次の英語による口頭試験突破にどうしても自信が持てず対策を考えてほしいというものでした。当時、英検準1級、TOEIC800点を同時に目指されて勉強されていましたが、どうしても英語を話し書く力が向上せず悩まれていました。いくつかの英語学校に2年ほど通った後のことでした。当教室で秋の教員採用二次面接試験対策、英検、TOEIC対策の勉強を開始されたのは、7年前の6月のことでした。
過去問題をベースにした二次試験予想問題を作成し教員試験に備えると共にTOEIC対策、英検のライティング問題及び二次試験対策と盛りだくさんの内容で、週2回1回3時間に渡る勉強を開始したのです。準備をする中で、ご自身が学んできた英語と当教室の英語指導の内容とのギャップに驚嘆されることしばしばでした。仮定表現の多様さ、現在形の持つ意味、collocation(繋がり表現)の大切さ、英語の表現ベースでのくくり方、等々様々な内容を入れ込んで、ご本人が教壇に立たれることを前提に授業を進めました。無論、教員試験二次対策は、過去問から予想問題を作成しシュミレーション中心の授業を組み立てました。
結果は、教員採用二次英語面接試験合格、英検準1級合格、TOEIC785点取得という素晴らしいものでした。これは目標を達成したいという学習者の心の強さと、英語には学び方があるのだということを認識させてくれるものでした。
この生徒さんは、今23区内の公立中学で教鞭をとっています。このことをきっかけに中学高校教員研修講座を開設したのですが、その後はこの講座に対する問い合わせもほとんどなく、5年近い月日が流れてしまいました。ところがつい先日、ある中学の英語教諭の方あらメールをいただきました。メールの大まかな趣旨は、英語の文法・語彙・リスニングと包括的にご自身の力を不安に感じられ、再度勉強し直したいというものでした。こうした教師の方々がいることを再認識すると同時に、この教諭の方のお力になりたいと強く思いました。人は、日々仕事をこなしながら過ごしていると、敢えて自分自身と取り巻く環境の中で本当にやらなくてはならないことを考える機会を見失いがちになります。この先生は、敢えてご自身の将来と現状を照らし合わせ、今やらなくてはならないことを見出されたのだと感慨に浸りました。現在はまだメールでのやりとりで行動を開始する時期を模索中ですが、指導することを念頭にした教材を更に充実したものにするため開発に着手したところです。義務教育内で行われている英語教育を言葉としてより実用的なものに変容させるためには、こうした教員の方々の双肩に掛かっていると言ってもよいかもしれません。正し、それには行政側の理解と支援が不可欠であることもまた事実であると考えます。
年内から来年にかけこの「中学高校英語教員研修講座」を新たな講座としてスタートさせようと思案中です。
今回は、最近の出来事と英語を指導すること関連についてお話しするだけで、長くなってしまいました。次回は、このことも踏まえて、前回までの話に軌道修正し「英語の語学感覚と指導姿勢」についてお話しします。
英語の指導って? 英語教室GP
2014年06月21日
梅雨入りして風雨の強い日が続いたかと思ったら、今度は梅雨はどこに?っといった天候が続いていますね。毎度のことながら、毎年感じる気候変動への懸念は止むことがありません。自分が子供の頃のクリアな季節の変化が徐々に失われていくようで心配になります。気候は人力では代えがたい現象、少しでも環境にダミッジを与えない生活を送らなければならないと戒める日々が続きそうですね。
前回最後にお伝えしましたように、今日は少し現実的に望ましいと思われる英語の学習指導の姿を、当教室で実践している方法を含めながらお話しようと思います。
英語に限らず言語を構成しているのは、語彙・ルール・音声・構文・組み合わせ、そしてそれらを蓄積した後の運用であると言うことができます。運用とは、無論書いたり話したりすることを意味します。ここで気づくことは、これらの言語の構成要素をばらばらにして学習者に指導する必要があるかということです。勿論、答えはNo!です。語学指導者の方々ならお分かりと思いますが、文字の組み合わせによってできている語彙レベルのことを最初に学習すれば、その後は実際の文章や言葉として使われている音声素材を直ぐに読み聞きする段階に入ることが極めて効果的な学習効果を生むことは周知のことかと考えます。
教室では、中学になったばかりの子供にアルファベットとそれからなる意味の塊としての語を指導した後は、いきなりセンテンスや会話の聞き取り練習に入ります。更には、一定の長さのトークを音声で聞いて内容把握の練習をします。大人の方々にもアルファベットの導入以外は、同じプロセスで授業を実施します。
聞いたり読んだりしていく中では、当然のことながら分からないことが山ほど出てきます。そこで登場するのがルールと語彙説明です。センテンスごとに聞いていく中で、また読んでいく中で表現や語法について徹底的に解説していきます。語順、ワードチョイス、構文など日本語との相違点に触れながら詳細な理解を促します。
これを実践するためには、指導者側の語学感覚は極めて重要な要素になります。当方は自分自身の教室での英語指導に加えて、外部の国際関連教育センターで帰国子女の日本及び海外の大学進学のための受験指導やTOEFLの対策指導を行っています。他の講師の方々とは頻繁に英語表現や語の用法について議論することがあります。ネイティブを含めた議論になることも頻繁です。こうした議論や自己研鑽、ネイティブとの実際のコミュニケーションの中から初めて指導者としての語学感覚が身に付きます。自分の経験のみに頼った独り善がりの指導方法は、極めて危険性の高いものになってしまうと言ってよいでしょう。
こうした語学感覚を今度はどうやって指導方法や指導構成に反映させていったらよいのでしょうか。次回はその点について少々お話を…。
前回最後にお伝えしましたように、今日は少し現実的に望ましいと思われる英語の学習指導の姿を、当教室で実践している方法を含めながらお話しようと思います。
英語に限らず言語を構成しているのは、語彙・ルール・音声・構文・組み合わせ、そしてそれらを蓄積した後の運用であると言うことができます。運用とは、無論書いたり話したりすることを意味します。ここで気づくことは、これらの言語の構成要素をばらばらにして学習者に指導する必要があるかということです。勿論、答えはNo!です。語学指導者の方々ならお分かりと思いますが、文字の組み合わせによってできている語彙レベルのことを最初に学習すれば、その後は実際の文章や言葉として使われている音声素材を直ぐに読み聞きする段階に入ることが極めて効果的な学習効果を生むことは周知のことかと考えます。
教室では、中学になったばかりの子供にアルファベットとそれからなる意味の塊としての語を指導した後は、いきなりセンテンスや会話の聞き取り練習に入ります。更には、一定の長さのトークを音声で聞いて内容把握の練習をします。大人の方々にもアルファベットの導入以外は、同じプロセスで授業を実施します。
聞いたり読んだりしていく中では、当然のことながら分からないことが山ほど出てきます。そこで登場するのがルールと語彙説明です。センテンスごとに聞いていく中で、また読んでいく中で表現や語法について徹底的に解説していきます。語順、ワードチョイス、構文など日本語との相違点に触れながら詳細な理解を促します。
これを実践するためには、指導者側の語学感覚は極めて重要な要素になります。当方は自分自身の教室での英語指導に加えて、外部の国際関連教育センターで帰国子女の日本及び海外の大学進学のための受験指導やTOEFLの対策指導を行っています。他の講師の方々とは頻繁に英語表現や語の用法について議論することがあります。ネイティブを含めた議論になることも頻繁です。こうした議論や自己研鑽、ネイティブとの実際のコミュニケーションの中から初めて指導者としての語学感覚が身に付きます。自分の経験のみに頼った独り善がりの指導方法は、極めて危険性の高いものになってしまうと言ってよいでしょう。
こうした語学感覚を今度はどうやって指導方法や指導構成に反映させていったらよいのでしょうか。次回はその点について少々お話を…。
英語教育の今後は? 英語教室GP
2014年06月08日
こんにちは。梅雨に入り稀にみる風雨に見舞われていますが、それがもたらす被害が心配です。まずは自分自身と身近にいる人達の安全に注意しながらこの時期を過ごして行きましょう。でもその反面、雨に濡れた青紫の紫陽花を偶然目にしたりすると幸せになれるのもこの時期ならではかもしれませんね。
これまでこのブログでは英語を言葉として位置づけし、総合的に学ぶことで運用力をつけることの重要性についてお話することが度々ありましたが、前回はこれを更に発展させて教育の目的や方向性を他の学習項目(数学・科学・社会・国語等)と関連付け、学際的アプローチを基盤にした教育の枠組み作りにまで発展さて考えてみました。しかし、これを精緻で現実的なモデルに仕上げる前に、もう少し英語そのもの学び方について考え直さなければならない事があります。
当教室の大人の生徒さんの大半が、分詞構文、仮定法など用語に聞き覚えはあるがそれが実際の英語という言語の中でどう表現され、どんなルールや経緯に基づいて考え出されてきたかを認識している方は、実際のところ極めて少ないです。例えば、こちらが「分詞構文でご存知ですか。」とお尋ねすると「アー、分詞構文ですね、知っています。でもそれって英語ではどんな表現でしたっけ。」といったお答えが戻ってくることがしばしばです。ここで、文法用語を多用して、それをベースに指導することの虚しさともいえる結果に直面します。ですから用語は使い方次第であることを忘れず、その過度な使用から生じる弊害に配慮し、指導する側がそれを使用することの有用性と無価値な側面両方を認識して指導にあたらなければならないのです。
前回お話した学際的な視野に立った英語教育を現実の教育現場の中で実現する以前の問題として、英語を身に付ける上で不可欠な要素を確認しておくことがまずは大切です。
義務教育の中での英語学習は、文法、単語、読解、リスニング、少ないですが会話、といったほぼ横の繋がりのない授業設定で実施されることが多いと思います。また大学生、社会人になっても、TOEIC等のスコアを向上させることが求められ、語彙を単独で記憶したり、文法事項、リスニングを別々の教材を使って学習することが多いですね。かく言う自分自身も米国の大学院に入るためにTOEFLやGREの勉強を机にしがみついて、一日8時間以上も対策教材に費やした経験があります。
こうした努力は決して無駄にはならないでしょうが、結果として、言葉としての英語を身に付けることにどれだけ役立つのでしょうか。何故、文法を勉強するのか、なぜ単語を覚えるのか、しっかりと到達点を明確にして英語は教えられているのでしょうか。またTOEICのスコアを向上させることと実務をどう関連付けて、企業は社員にその必要性を説明し求めているのでしょうか。
言葉は、聞いたり話したり、読んだり書いたりする力が、総合的に身についていなければ真の意味において役にも立ちません。縦割り方式で英語学習をしていても横の繋がりを考えて最終目標をしっかりと認識して学んでいかなければ、費やした時間は0になってしまいます。とにかくあらゆる環境を利用して、学習者が受け身ではなく自らが言語を使う場面を設けることが何よりも優先されなければならないでしょう。もしそれを実際に形にしていくとするならば…について次回はお話します。
これまでこのブログでは英語を言葉として位置づけし、総合的に学ぶことで運用力をつけることの重要性についてお話することが度々ありましたが、前回はこれを更に発展させて教育の目的や方向性を他の学習項目(数学・科学・社会・国語等)と関連付け、学際的アプローチを基盤にした教育の枠組み作りにまで発展さて考えてみました。しかし、これを精緻で現実的なモデルに仕上げる前に、もう少し英語そのもの学び方について考え直さなければならない事があります。
当教室の大人の生徒さんの大半が、分詞構文、仮定法など用語に聞き覚えはあるがそれが実際の英語という言語の中でどう表現され、どんなルールや経緯に基づいて考え出されてきたかを認識している方は、実際のところ極めて少ないです。例えば、こちらが「分詞構文でご存知ですか。」とお尋ねすると「アー、分詞構文ですね、知っています。でもそれって英語ではどんな表現でしたっけ。」といったお答えが戻ってくることがしばしばです。ここで、文法用語を多用して、それをベースに指導することの虚しさともいえる結果に直面します。ですから用語は使い方次第であることを忘れず、その過度な使用から生じる弊害に配慮し、指導する側がそれを使用することの有用性と無価値な側面両方を認識して指導にあたらなければならないのです。
前回お話した学際的な視野に立った英語教育を現実の教育現場の中で実現する以前の問題として、英語を身に付ける上で不可欠な要素を確認しておくことがまずは大切です。
義務教育の中での英語学習は、文法、単語、読解、リスニング、少ないですが会話、といったほぼ横の繋がりのない授業設定で実施されることが多いと思います。また大学生、社会人になっても、TOEIC等のスコアを向上させることが求められ、語彙を単独で記憶したり、文法事項、リスニングを別々の教材を使って学習することが多いですね。かく言う自分自身も米国の大学院に入るためにTOEFLやGREの勉強を机にしがみついて、一日8時間以上も対策教材に費やした経験があります。
こうした努力は決して無駄にはならないでしょうが、結果として、言葉としての英語を身に付けることにどれだけ役立つのでしょうか。何故、文法を勉強するのか、なぜ単語を覚えるのか、しっかりと到達点を明確にして英語は教えられているのでしょうか。またTOEICのスコアを向上させることと実務をどう関連付けて、企業は社員にその必要性を説明し求めているのでしょうか。
言葉は、聞いたり話したり、読んだり書いたりする力が、総合的に身についていなければ真の意味において役にも立ちません。縦割り方式で英語学習をしていても横の繋がりを考えて最終目標をしっかりと認識して学んでいかなければ、費やした時間は0になってしまいます。とにかくあらゆる環境を利用して、学習者が受け身ではなく自らが言語を使う場面を設けることが何よりも優先されなければならないでしょう。もしそれを実際に形にしていくとするならば…について次回はお話します。
英語教育の未来!! 英語教室GP
2014年06月01日
いよいよ6月、梅雨を経て夏の様相をも感じる季節に移り変わっていきますね。自分の生活が1年という周期で動いていることを改めて実感します。ただ年ごとに感じる気候の変動と地震に象徴される自然災害には懸念を覚えると共に、自他に対する配慮を忘れることなく進んでいかなくてはと年を取るごとに思いが深まります。
前回は、現在の英語教育の不思議について、現場からの声を含めて語らせていただきました。今回もその続きを…。
東京オリンピックの招致も実現し、止むことのない経済発展を目指す国の方向性を背景に、英語をやはり身に付けてく必要があると考える方々、今後更に増えていくことが想定できますね。社会人の方々は目の前に迫りくる現実からその必要性を実感し、英語習得に足を踏み出されることも多くなっていることを感じます。他方において、教育過程に身を置いている10代の若者たちは、英語学習をどんな姿勢をもって受けとめているのでしょうか。
教える側、主に教育政策を立案実施し指導していく側は、議論と試行錯誤の渦中で「国際人の創出」という長い歴史を持つ表現を用い改革を進めつつありますね。英語教育を小学校の中学年から導入するなど、ある意味画期的な方策を採用することを思案中のようです。
思考力や発想力は、言うまでもなく自国の言葉によって養われ表現されるものです。この基盤なしで表面的な他言語の力を身に付けたとしても、他者の思考に訴えることのない形骸的なコミュニケーション力を身につけるに過ぎないことになります。まずは母語によって思考力、論理力、言語構成力を身につけることが、何よりも「国際人材」を生み出す上で必要なことです。母語に優れた人間は、必ず真の意味で秀でた他言語の力を身に付けることができると確信しています。
こうした人の脳の発達過程を策定者が知らないのか、又は見失っているのかは不明ですが、英語をできるだけ早い時期に導入することが国際人の創出に繋がるという短絡的な発想が今後の教育過程の方向性の主流になりつつあり、いささかの懸念を感じています。言葉の学習を始める上で大切なことは、時期ではなく、言語の重要性に基づいた効果的かつ実践的な内容のプログラムを一刻も早く作り上げることと、そのプログラムの中に英語を学ぶことが何故必要なのかを明確に説得力に満ちた説明を含めることです。これは学問でいうところの学際的アプローチに該当するやり方を実践していくことを意味しています。つまりこれは、数学や科学の知識は人間生活をより無駄のない環境や生態系の保全のために不可欠な技術革新の原動力になるため、教育課程の中で取り扱うのだということを強調しつつ、それを基盤にした研究開発とその成果を国際的規模で広めていくためには他国の人々とのコミュニケーションができなければならないことを教育の大きな枠組みとして位置付けるということと一致します。ここに言語力と他分野の知識と学際的価値が見出されるのです。
ここで間違えてはならないのは、何も専門的知識や実習教育を教育課程に取り込むとい意味ではないということです。あくまでも指導する内容、具体的には科目の横の繋がり、つまり相互作用から生まれる相乗効果と一体感を教育の中に反映させることが何よりも大切なのです。
このことを実現するためには、現在の制度下にある教育者の見地のみで判断するのではなく、民間企業や公的機関の人材を巻き込んでカリキュラムの作りこみをする必要があります。産学官が一体となって教育の方向性を明確にし、若い世代の能力や才能を学際的見地から最大限に引き出す体制づくりを真剣に開始する時期がきています。今後10年、いや50年先の日本の更なる少子化進行に象徴される人口構成から考えても、この作業は急を要すると考えざるをえません。更にその先100年後のこの国…心配です。
今回は、英語教育を取り巻く環境づくりについての考えをお伝えしました。次回は英語教育の今後望まれる未来像について、詳細な内容に触れながらお話したいと思案中です。
前回は、現在の英語教育の不思議について、現場からの声を含めて語らせていただきました。今回もその続きを…。
東京オリンピックの招致も実現し、止むことのない経済発展を目指す国の方向性を背景に、英語をやはり身に付けてく必要があると考える方々、今後更に増えていくことが想定できますね。社会人の方々は目の前に迫りくる現実からその必要性を実感し、英語習得に足を踏み出されることも多くなっていることを感じます。他方において、教育過程に身を置いている10代の若者たちは、英語学習をどんな姿勢をもって受けとめているのでしょうか。
教える側、主に教育政策を立案実施し指導していく側は、議論と試行錯誤の渦中で「国際人の創出」という長い歴史を持つ表現を用い改革を進めつつありますね。英語教育を小学校の中学年から導入するなど、ある意味画期的な方策を採用することを思案中のようです。
思考力や発想力は、言うまでもなく自国の言葉によって養われ表現されるものです。この基盤なしで表面的な他言語の力を身に付けたとしても、他者の思考に訴えることのない形骸的なコミュニケーション力を身につけるに過ぎないことになります。まずは母語によって思考力、論理力、言語構成力を身につけることが、何よりも「国際人材」を生み出す上で必要なことです。母語に優れた人間は、必ず真の意味で秀でた他言語の力を身に付けることができると確信しています。
こうした人の脳の発達過程を策定者が知らないのか、又は見失っているのかは不明ですが、英語をできるだけ早い時期に導入することが国際人の創出に繋がるという短絡的な発想が今後の教育過程の方向性の主流になりつつあり、いささかの懸念を感じています。言葉の学習を始める上で大切なことは、時期ではなく、言語の重要性に基づいた効果的かつ実践的な内容のプログラムを一刻も早く作り上げることと、そのプログラムの中に英語を学ぶことが何故必要なのかを明確に説得力に満ちた説明を含めることです。これは学問でいうところの学際的アプローチに該当するやり方を実践していくことを意味しています。つまりこれは、数学や科学の知識は人間生活をより無駄のない環境や生態系の保全のために不可欠な技術革新の原動力になるため、教育課程の中で取り扱うのだということを強調しつつ、それを基盤にした研究開発とその成果を国際的規模で広めていくためには他国の人々とのコミュニケーションができなければならないことを教育の大きな枠組みとして位置付けるということと一致します。ここに言語力と他分野の知識と学際的価値が見出されるのです。
ここで間違えてはならないのは、何も専門的知識や実習教育を教育課程に取り込むとい意味ではないということです。あくまでも指導する内容、具体的には科目の横の繋がり、つまり相互作用から生まれる相乗効果と一体感を教育の中に反映させることが何よりも大切なのです。
このことを実現するためには、現在の制度下にある教育者の見地のみで判断するのではなく、民間企業や公的機関の人材を巻き込んでカリキュラムの作りこみをする必要があります。産学官が一体となって教育の方向性を明確にし、若い世代の能力や才能を学際的見地から最大限に引き出す体制づくりを真剣に開始する時期がきています。今後10年、いや50年先の日本の更なる少子化進行に象徴される人口構成から考えても、この作業は急を要すると考えざるをえません。更にその先100年後のこの国…心配です。
今回は、英語教育を取り巻く環境づくりについての考えをお伝えしました。次回は英語教育の今後望まれる未来像について、詳細な内容に触れながらお話したいと思案中です。
新しい生徒さんとまず話すことって? 英語教室GP
2014年05月25日
毎度のことながら、時の流れは全くもって速く追いかけられるように過ぎていきますね。もう5月も終わりに近づいているとは…。と言いながらも確実にその時その時にやらなくてはならないことはあるもの、それを見極めながら進んで行けるように自戒しつつ過ごしていきたいものです。
最近入っていらっしゃった生徒さん達と共通して話す話題について、今日は少しだけ…。よく言われることではあるのですが、その話題とは「日本の中学高校で6年間英語を勉強しているのに、何故高校卒業の段階で英語を母語としている方々と会話ができなかったり、英語で文章が書けないのでしょうか。」というものです。改めて確かにそうですよね。生徒さん達は、その原因をご自身の取り組み方に帰着される方が多いのですが。例えば「中学の時、文法が苦手でアルファベットを見るのが嫌いになった。」「高校の先生と相性がよくなく勉強しなかった。」「文法用語は多少覚えているのに、それが英語ではどう表現するものなのか完全に忘れてしまっている。」等、その原因は様々です。
当方の限られてはいますが教育現場における英語教育に関する情報を鑑みると、現在の中学高校のカリキュラムでは、到底6年間英語を学習したとしても言葉としての運用前提の英語力を身に付けることは困難かと思います。英語ネイティブ講師の授業を取り入れたり、リスニングに費やす時間を増やしたりと、国際化を目指す教育政策と連動した学校教育の努力はされていますが、それが使える言語としての英語に大きく貢献していますでしょうか。
当教室の生徒さん達は英語に大学まで関わっていたのに、聞くことはある程度できても言いたいことも書きたいことも表現できない理由を自分自身の中に求める謙虚さをもっていらっしゃいますが、それが真実なのか疑問にも思えます。確かに英語に限らず学ぶことは自分の姿勢や考え方次第です。でも今の英語教育には多くの改善する余地があると思えてなりません。今後何回かは、大人の方々の英語習得も絡めながらどうしたら6年間の英語教育が実効あるものになるのか考えてみたいと思っています。そうすることで前回までの学習方法についての考えも総括していきます。
最近入っていらっしゃった生徒さん達と共通して話す話題について、今日は少しだけ…。よく言われることではあるのですが、その話題とは「日本の中学高校で6年間英語を勉強しているのに、何故高校卒業の段階で英語を母語としている方々と会話ができなかったり、英語で文章が書けないのでしょうか。」というものです。改めて確かにそうですよね。生徒さん達は、その原因をご自身の取り組み方に帰着される方が多いのですが。例えば「中学の時、文法が苦手でアルファベットを見るのが嫌いになった。」「高校の先生と相性がよくなく勉強しなかった。」「文法用語は多少覚えているのに、それが英語ではどう表現するものなのか完全に忘れてしまっている。」等、その原因は様々です。
当方の限られてはいますが教育現場における英語教育に関する情報を鑑みると、現在の中学高校のカリキュラムでは、到底6年間英語を学習したとしても言葉としての運用前提の英語力を身に付けることは困難かと思います。英語ネイティブ講師の授業を取り入れたり、リスニングに費やす時間を増やしたりと、国際化を目指す教育政策と連動した学校教育の努力はされていますが、それが使える言語としての英語に大きく貢献していますでしょうか。
当教室の生徒さん達は英語に大学まで関わっていたのに、聞くことはある程度できても言いたいことも書きたいことも表現できない理由を自分自身の中に求める謙虚さをもっていらっしゃいますが、それが真実なのか疑問にも思えます。確かに英語に限らず学ぶことは自分の姿勢や考え方次第です。でも今の英語教育には多くの改善する余地があると思えてなりません。今後何回かは、大人の方々の英語習得も絡めながらどうしたら6年間の英語教育が実効あるものになるのか考えてみたいと思っています。そうすることで前回までの学習方法についての考えも総括していきます。
連休こそ英語、そしてその後も!! 英語教室GP
2014年05月03日
いよいよGW後半ですね。日頃の疲れをとるために、旅行や帰省、昔の友人と会うよい機会です。どうか有意義な解放感溢れるお休みをお過ごしください。
当方といえば、休みなしの連続授業!! これもまた一つの過ごし方です。 今、ちょっと気になるのは、3年間1度も休むことなく通ってくださっていたノブさん(IT企業管理職)が、2週連続でお休みになっていること。当方にはその理由の推測はできますが、何とも寂しい気持ちです。企業が遂行する事業は、ビジネスとしての発展を重視するため、サービスを受ける側の事情が事細かに見えなくなることがあります。そんな時、企業はお客さんからのニーズや、場合によっては辛辣な批判を受けることもあります。そんな状況にノブさんは立たされ、その対応に追われているのだろうなと、考えながら声は届かなくても応援の言葉を送っています。
誰でも道を進んで行く時は、苦難や問題にぶち当たります、例えそれが自分が原因の元でなくても、それを背負って耐え忍んで切り抜けなければならないことは多いですね。ノブさんが持つ生来の根性と積み上げてきた経験によって、現状を切り抜け早く教室に復帰してくれることを願うばかりです。
ところで、長期の連休、社会が授けてくれる機会を是非有意義にお過ごしください。英語は1年ごとの周期というより、日々の生活の中で常にどんな時でも、その気があれば接し磨くことができるものです。連休は特に今までの英語との接し方や今後の歩み方を落ち着いて考え、実行するよい機会なのかもしれません。
ノブさんのように、一時期止むを得ず中断せざるを得なくても、またいつからでも再開できる学びごと、つまり自分自身の内部に財産をつくることのできるよい学び対象だと感じます。
「GW休暇、そしてその後も英語を指導することに邁進します。」 と言いながら、ちょっと休んで温泉でも行きたくなるのがこの時期ですね。
当方といえば、休みなしの連続授業!! これもまた一つの過ごし方です。 今、ちょっと気になるのは、3年間1度も休むことなく通ってくださっていたノブさん(IT企業管理職)が、2週連続でお休みになっていること。当方にはその理由の推測はできますが、何とも寂しい気持ちです。企業が遂行する事業は、ビジネスとしての発展を重視するため、サービスを受ける側の事情が事細かに見えなくなることがあります。そんな時、企業はお客さんからのニーズや、場合によっては辛辣な批判を受けることもあります。そんな状況にノブさんは立たされ、その対応に追われているのだろうなと、考えながら声は届かなくても応援の言葉を送っています。
誰でも道を進んで行く時は、苦難や問題にぶち当たります、例えそれが自分が原因の元でなくても、それを背負って耐え忍んで切り抜けなければならないことは多いですね。ノブさんが持つ生来の根性と積み上げてきた経験によって、現状を切り抜け早く教室に復帰してくれることを願うばかりです。
ところで、長期の連休、社会が授けてくれる機会を是非有意義にお過ごしください。英語は1年ごとの周期というより、日々の生活の中で常にどんな時でも、その気があれば接し磨くことができるものです。連休は特に今までの英語との接し方や今後の歩み方を落ち着いて考え、実行するよい機会なのかもしれません。
ノブさんのように、一時期止むを得ず中断せざるを得なくても、またいつからでも再開できる学びごと、つまり自分自身の内部に財産をつくることのできるよい学び対象だと感じます。
「GW休暇、そしてその後も英語を指導することに邁進します。」 と言いながら、ちょっと休んで温泉でも行きたくなるのがこの時期ですね。
「母子で英語」も1つの学び方!! 英語教室GP
2014年03月30日
いよいよ春本番といった気候になってきましたね。桜の蕾も
一気に膨らみ、例年の華麗な姿を見せてくれるのも近いと
感じます。季節とその中で生き続けている自然のサイクル
は、当たり前のようで実に神秘的なものです。大気の温度
や降水量、自然から与えられる条件の下、それに逆らうこ
と無しにあるがまま享受し同じ時期に同じ姿を見せてくれる
ことは当たり前のようで、陰で微妙なバランスが保たれてい
なければ不可能な現象にも思えます。そんな当たり前では
あるけれど、巧みなバランスに保たれている周期をいつま
でも壊さずに過ごせたらよいと願うばかりです。
人の生活にもバランスは極めて重要ですね。一つのこと、
一人の人に偏重しすぎると脆さが露呈し、時として問題を
引き起こします。昨年末12月26日に、当教室に一本の電
話がありました。お子さんが中学3年生、大学付属の中学
に通う中三の息子さんをもつお母様からでした。高校に上
がるには、かなりの高い水準が設定されていて、中学の
総合平均点が60点以上でないと、進学できないとのこと。
特に英語の成績が下降気味でどうにか3学期の成績を基
準に届くように指導をという内容でした。無論、承知いた
しました。その電話後、面談の後に早速今年一月からプ
ライベイトレッスンで準備開始の予定を組みました。話は
これだけで終わらないのですが…
その面談をした翌日、お母様からメールをいただきました。
趣旨は「子供に勉強するように言うのは親の務めだと思い
ますが、言うからには自分も学ぶということを実行しなけれ
ば説得力がないですよね。自分も教室に通います。」とい
うものでした。確かにお子さんに勉強をするように伝えるこ
とは、親御さんの大切な接し方の1つです。でも自分も新た
に学ぶことの大変さややりがいを体験することで、子供に
対し間接的に親としてのできる教育を実践されようとするお
母様の考え方に感心させられました。無論、気持ちや考え
方に加え、時間やお金といった物理的、経済的な条件も揃
わないとできないことではありますが、一本、筋の通った姿
勢は、当方の今後の道の歩み方に対して刺激を与えてくれ
、また教えられることの多い出来事でもありました。
現在では、息子さんの高校進学も決まり、別の日にお二人
で教室に通っていただいています。そして指導差し上げな
がら改めて、英語を学ぶ目的は状況が違っていても同じな
のだな、ということ。つまり言葉として使えるようになること。
この目標無くして、また学ぶことの意味も発見できません。
一気に膨らみ、例年の華麗な姿を見せてくれるのも近いと
感じます。季節とその中で生き続けている自然のサイクル
は、当たり前のようで実に神秘的なものです。大気の温度
や降水量、自然から与えられる条件の下、それに逆らうこ
と無しにあるがまま享受し同じ時期に同じ姿を見せてくれる
ことは当たり前のようで、陰で微妙なバランスが保たれてい
なければ不可能な現象にも思えます。そんな当たり前では
あるけれど、巧みなバランスに保たれている周期をいつま
でも壊さずに過ごせたらよいと願うばかりです。
人の生活にもバランスは極めて重要ですね。一つのこと、
一人の人に偏重しすぎると脆さが露呈し、時として問題を
引き起こします。昨年末12月26日に、当教室に一本の電
話がありました。お子さんが中学3年生、大学付属の中学
に通う中三の息子さんをもつお母様からでした。高校に上
がるには、かなりの高い水準が設定されていて、中学の
総合平均点が60点以上でないと、進学できないとのこと。
特に英語の成績が下降気味でどうにか3学期の成績を基
準に届くように指導をという内容でした。無論、承知いた
しました。その電話後、面談の後に早速今年一月からプ
ライベイトレッスンで準備開始の予定を組みました。話は
これだけで終わらないのですが…
その面談をした翌日、お母様からメールをいただきました。
趣旨は「子供に勉強するように言うのは親の務めだと思い
ますが、言うからには自分も学ぶということを実行しなけれ
ば説得力がないですよね。自分も教室に通います。」とい
うものでした。確かにお子さんに勉強をするように伝えるこ
とは、親御さんの大切な接し方の1つです。でも自分も新た
に学ぶことの大変さややりがいを体験することで、子供に
対し間接的に親としてのできる教育を実践されようとするお
母様の考え方に感心させられました。無論、気持ちや考え
方に加え、時間やお金といった物理的、経済的な条件も揃
わないとできないことではありますが、一本、筋の通った姿
勢は、当方の今後の道の歩み方に対して刺激を与えてくれ
、また教えられることの多い出来事でもありました。
現在では、息子さんの高校進学も決まり、別の日にお二人
で教室に通っていただいています。そして指導差し上げな
がら改めて、英語を学ぶ目的は状況が違っていても同じな
のだな、ということ。つまり言葉として使えるようになること。
この目標無くして、また学ぶことの意味も発見できません。
英語を学ぶ年齢は? 英語教室GP
2014年03月09日
こんにちは。
春からの新しいスタートに向けて準備が始まる時期になりましたね。進学
、就職など新しい環境へ向かう前章の時です。毎年のことでありながら1
年に1度しかお目にかかれない桜の花の開花もまた待ち遠しいです。
今日は、時折教室の生徒さんやお問い合わせいただく方から尋ねられる
質問について少しお話を…
1番多いご質問は、英語は年齢が高いとだめですよね。○○才ですが今か
らでも英語習得は、間に合いますか。」という問いです。一言で言って、言
葉を学ぶことに年齢は関係ないと思います。なぜなら言葉のルール、語彙
、表現を理解しながら覚えたり、聞いて発音を覚え話す練習することに年
齢が何の関係があるのでしょうか。言葉は、自分がそれを身に付けたいか
どうかが全てです。また必要性に迫られ前向きにではないにしてもコツコツ
と積み上げていけば、年齢に関わらず言葉は身に付きます。無論、母語で
はないのですからそれと同じレベルに到達することは至難の業ですが、英
語を母語とする人々とコミュニケーションするだけの英語力は、前向きさと
ある程度の忍耐、そして何よりも英語で話したり書いたり、また聞くこと読
むことをしたいという思いがあれば必ず身につくものです。
ここ2、3年中学高校生の生徒さんが増えつつあることは以前にもお伝えし
ましたが、子供たちも一度理解したことをこちらがびっくりするくらいすっき
り忘れてくれます。勿論、毎日のように英語に浸り復習を欠かさない子供
は著しい伸びを見せてくれますが、半分以上の子供は前回やったことの
半分も覚えていないことが多いです。10代の一番脳が活性化する時期に
こうも簡単に忘れるのか。答えは1つです。一旦理解したことや聞いた音声
を復習せず聞き直すこともしないからです。それを繰り返している限りいつ
も語学力はゼロに戻ってしまいます。1日おきにでもいいからやったことを
繰り返す、これ以外に語学力を向上させる道はありません。別の言い方を
すれば、大人、子供に関わらず頭と耳で理解したことを繰り返しによって
忘れずに積み上げていけば、必ず英語は身に付くというこが言えます。当
教室の高校大学受験生には、復習を必ずしてもらい復習クイズをしてはい
ますが…
当方は、英語を26歳から本格的に学び始めました。大学受験までの英語
は、文法や読解といった英語という言語の一側面のみを取り上げ、その力
を身に付けていただけで言葉としての英語を身に付けようと気づいたのは、
米国大学院に行くための勉強を始めた時からでした。この準備の過程で、
繰り返すことの重要性をどれだけ痛感したことか…。
英語を始めることに何の躊躇もいりません。聞いて読み、ルールや表現を
覚えて書いて話すことができることがどんなに自分自身に充実感をもたら
してくれるか。また違った世界を見ることができるか、想像しただけでわくわ
くするような英語の学び方が何より必要なのではないでしょうかね。それは
覚えたことを忘れずにいる自分に誇りを感じられるまで、英語に浸ることか
ら生まれてくるのではと考えています。
春からの新しいスタートに向けて準備が始まる時期になりましたね。進学
、就職など新しい環境へ向かう前章の時です。毎年のことでありながら1
年に1度しかお目にかかれない桜の花の開花もまた待ち遠しいです。
今日は、時折教室の生徒さんやお問い合わせいただく方から尋ねられる
質問について少しお話を…
1番多いご質問は、英語は年齢が高いとだめですよね。○○才ですが今か
らでも英語習得は、間に合いますか。」という問いです。一言で言って、言
葉を学ぶことに年齢は関係ないと思います。なぜなら言葉のルール、語彙
、表現を理解しながら覚えたり、聞いて発音を覚え話す練習することに年
齢が何の関係があるのでしょうか。言葉は、自分がそれを身に付けたいか
どうかが全てです。また必要性に迫られ前向きにではないにしてもコツコツ
と積み上げていけば、年齢に関わらず言葉は身に付きます。無論、母語で
はないのですからそれと同じレベルに到達することは至難の業ですが、英
語を母語とする人々とコミュニケーションするだけの英語力は、前向きさと
ある程度の忍耐、そして何よりも英語で話したり書いたり、また聞くこと読
むことをしたいという思いがあれば必ず身につくものです。
ここ2、3年中学高校生の生徒さんが増えつつあることは以前にもお伝えし
ましたが、子供たちも一度理解したことをこちらがびっくりするくらいすっき
り忘れてくれます。勿論、毎日のように英語に浸り復習を欠かさない子供
は著しい伸びを見せてくれますが、半分以上の子供は前回やったことの
半分も覚えていないことが多いです。10代の一番脳が活性化する時期に
こうも簡単に忘れるのか。答えは1つです。一旦理解したことや聞いた音声
を復習せず聞き直すこともしないからです。それを繰り返している限りいつ
も語学力はゼロに戻ってしまいます。1日おきにでもいいからやったことを
繰り返す、これ以外に語学力を向上させる道はありません。別の言い方を
すれば、大人、子供に関わらず頭と耳で理解したことを繰り返しによって
忘れずに積み上げていけば、必ず英語は身に付くというこが言えます。当
教室の高校大学受験生には、復習を必ずしてもらい復習クイズをしてはい
ますが…
当方は、英語を26歳から本格的に学び始めました。大学受験までの英語
は、文法や読解といった英語という言語の一側面のみを取り上げ、その力
を身に付けていただけで言葉としての英語を身に付けようと気づいたのは、
米国大学院に行くための勉強を始めた時からでした。この準備の過程で、
繰り返すことの重要性をどれだけ痛感したことか…。
英語を始めることに何の躊躇もいりません。聞いて読み、ルールや表現を
覚えて書いて話すことができることがどんなに自分自身に充実感をもたら
してくれるか。また違った世界を見ることができるか、想像しただけでわくわ
くするような英語の学び方が何より必要なのではないでしょうかね。それは
覚えたことを忘れずにいる自分に誇りを感じられるまで、英語に浸ることか
ら生まれてくるのではと考えています。
春から英語‼ TOEIC講座も。。。
2014年02月19日
こんにちは。2週間連続で降った雪のために、かなりの食品類が
生産地域から輸送を妨げられて東京まで届いていないこと、コン
ビニやスパーで感じますね。震災の時もそうでしたが、普段感じ
ない不便さ?を改めて目の当たりにすると、逆に如何に便利さ
に慣れすぎているかを痛感せざるを得ません。限られた資源や
生産者の苦労、物の大切さなど再度認識し直さなければならな
い時期が来ている気がします。
ともあれ2月も後半に入り、春の風を感じる時も迫っている実感
が芽生え始めます。前々回お話した中学の英語クラス分け案に
ついてのコメントは少々お待ちください。今日は生徒さんに指導
差し上げながら感じることを少しだけ…
英語はバランスよく聞く、話す、読む、書くことを実践していくこと
が言葉としての英語をより早く効率的に身に付けることができる
ことは言うまでもありませんが、学ぶポイントとして最も大切な点
とは一体何なのでしょうかね。TOEICのような試験は知識ベース
のもので、語彙や読む力、聞く力を中心に評価するものですが、
これは言葉の一側面でしかありませんね。例えば、聞いてわかる
こととその聞いたことと同じ水準の表現を自分で書いたり話した
りすることは根本的に違う脳の部分を使って実現されます。聞い
て読むことはできても、書くこと話すことが出来ないのはそのため
ですね。
そこで当方のお薦めは、動詞を中心として語と語の繋がり表現で
きるだけ多く、理解に基づいて蓄積していくことです。つまり動詞
+目的語+to doといった動詞との連携で出来上がっている形をよ
り多く積み上げるのです。単純な話、lookのような語の意味のみ
を知っていてもほとんど言葉として運用力はつきません。単語テ
スト?はっきり言って意味ない時間の浪費ともいえる英語力のチ
ェック手法です。Lookはlook at, look over, look for, look out
for, look into, look in, look up to, look down on, look+形容詞
、look like+名詞、look like 主語+動詞のように日常的によく使わ
れる形態で覚え使ってみるということをしない限り、英語の総合
力自体向上しません。
3月8日、22日、暫定的ではあるのですがTOEIC「使う英語」講
座を再開します。この講座では、今申し上げたことを含め、英語
を使うことに焦点を絞り込んだ内容に組み立ててあります。この
ことを忘れずに学んでいけば、聞くこと読むことにも大きな効果
を及ぼすことは間違いありません。3月という春の正に初めから
、特に「いつかは英語を…」と思われている方の参加をお待ちし
たいと思います。無論、興味がある方々はどなたでも、お気兼ね
なく!!
次回は、もう少し英語についての学び方+指導の仕方について
考えをまた少しだけお話させてください。中学のクラス分けにつ
いても一言お話出来ればと思っています。
◆ お問い合わせ
電話: 042-486-2004
e-mail: good-performer@jcom.home.ne.jp
URL: http;//chofu.com/good-performer/
生産地域から輸送を妨げられて東京まで届いていないこと、コン
ビニやスパーで感じますね。震災の時もそうでしたが、普段感じ
ない不便さ?を改めて目の当たりにすると、逆に如何に便利さ
に慣れすぎているかを痛感せざるを得ません。限られた資源や
生産者の苦労、物の大切さなど再度認識し直さなければならな
い時期が来ている気がします。
ともあれ2月も後半に入り、春の風を感じる時も迫っている実感
が芽生え始めます。前々回お話した中学の英語クラス分け案に
ついてのコメントは少々お待ちください。今日は生徒さんに指導
差し上げながら感じることを少しだけ…
英語はバランスよく聞く、話す、読む、書くことを実践していくこと
が言葉としての英語をより早く効率的に身に付けることができる
ことは言うまでもありませんが、学ぶポイントとして最も大切な点
とは一体何なのでしょうかね。TOEICのような試験は知識ベース
のもので、語彙や読む力、聞く力を中心に評価するものですが、
これは言葉の一側面でしかありませんね。例えば、聞いてわかる
こととその聞いたことと同じ水準の表現を自分で書いたり話した
りすることは根本的に違う脳の部分を使って実現されます。聞い
て読むことはできても、書くこと話すことが出来ないのはそのため
ですね。
そこで当方のお薦めは、動詞を中心として語と語の繋がり表現で
きるだけ多く、理解に基づいて蓄積していくことです。つまり動詞
+目的語+to doといった動詞との連携で出来上がっている形をよ
り多く積み上げるのです。単純な話、lookのような語の意味のみ
を知っていてもほとんど言葉として運用力はつきません。単語テ
スト?はっきり言って意味ない時間の浪費ともいえる英語力のチ
ェック手法です。Lookはlook at, look over, look for, look out
for, look into, look in, look up to, look down on, look+形容詞
、look like+名詞、look like 主語+動詞のように日常的によく使わ
れる形態で覚え使ってみるということをしない限り、英語の総合
力自体向上しません。
3月8日、22日、暫定的ではあるのですがTOEIC「使う英語」講
座を再開します。この講座では、今申し上げたことを含め、英語
を使うことに焦点を絞り込んだ内容に組み立ててあります。この
ことを忘れずに学んでいけば、聞くこと読むことにも大きな効果
を及ぼすことは間違いありません。3月という春の正に初めから
、特に「いつかは英語を…」と思われている方の参加をお待ちし
たいと思います。無論、興味がある方々はどなたでも、お気兼ね
なく!!
次回は、もう少し英語についての学び方+指導の仕方について
考えをまた少しだけお話させてください。中学のクラス分けにつ
いても一言お話出来ればと思っています。
◆ お問い合わせ
電話: 042-486-2004
e-mail: good-performer@jcom.home.ne.jp
URL: http;//chofu.com/good-performer/